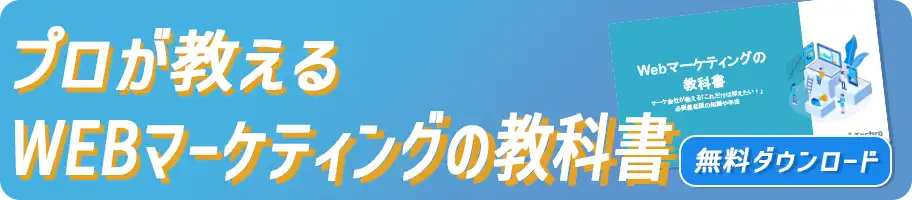SEO対策の記事作成依頼ガイド|費用相場から失敗しない外注先の選び方まで徹底解説
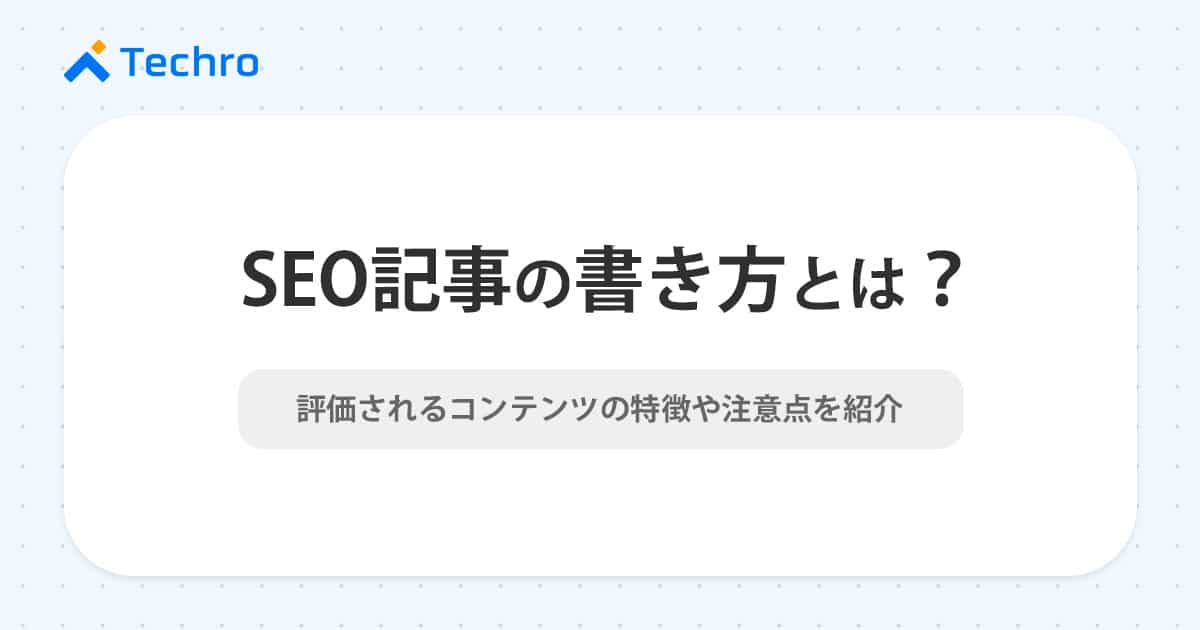
「SEOに強い記事を外注したいが、どこに頼めばいいかわからない」
「費用はどのくらいかかるのだろうか。絶対に失敗したくない」
このような悩みを抱えるWeb担当者様は少なくありません。
SEO対策において、質の高いコンテンツは事業成長のエンジンとなります。
しかし、社内にリソースやノウハウがない場合、記事作成の外注は有効な選択肢です。
本記事では、SEO記事作成の依頼に関する全知識を網羅的に解説します。
費用相場から信頼できる依頼先の選び方、最新のAI活用法、そして成果を出すためのポイントまで、専門家の視点で具体的にご紹介します。
この記事を読めば、貴社に最適なパートナーを見つけ、事業成長に繋がるコンテンツ投資を実現できるはずです。
なお、テクロ株式会社では「SEOのキーワード選定マニュアル」を無料で配布しています。
オウンドメディアで上位表示を獲得したいBtoB企業様はぜひご確認ください。
「SEOのキーワード選定マニュアル」をチェック!

- キーワード選定とは
- キーワード選定前に行うこと
- キーワード選定の手順
- キーワード選定の注意点
- おすすめのツール
BtoB企業様のオウンドメディアで実施しているテクロのキーワード選定の方法を公開しています。「SEOのキーワード選定マニュアル」をお気軽にダウンロードください。
目次
そもそもSEO記事作成の外注とは?依頼できる業務と依頼先の種類
まず、SEO記事作成を外部に委託するとは、具体的にどのような業務を依頼できるのでしょうか。
一般的に「記事作成の外注」というと、文章の執筆だけをイメージしがちです。
しかし実際には、戦略立案から効果測定まで、コンテンツマーケティングに関わる幅広い業務を依頼できます。
自社のリソースや課題に合わせて、どの業務を外部に任せるかを明確にすることが、外注成功の第一歩となります。
ここでは、依頼できる業務範囲と、主な依頼先の種類について解説します。
記事作成代行に依頼できる業務範囲
記事作成の外注と一言で言っても、その業務範囲は様々です。
依頼先によっては、企画から入稿までワンストップで対応してくれる場合もあります。
自社のリソース状況と照らし合わせ、どのフェーズを依頼するか検討しましょう。
| フェーズ | 主な業務内容 |
|---|---|
| 企画・戦略 | – SEOキーワードの選定・調査 – 競合サイトの分析 – ペルソナ・カスタマージャーニーの設計 – コンテンツ全体の戦略立案 |
| 構成作成 | – 記事構成案の作成(タイトル、見出し、導入・まとめ) – 盛り込むべき情報の整理 – 内部リンク設計 |
| 執筆 | – 記事本文のライティング – 取材・インタビューの実施 |
| 編集・入稿 | – 編集・校正・校閲 – コピーコンテンツチェック – トンマナ(文体や表記)の統一 – 画像選定・図解作成 – CMSへの入稿作業 |
| 分析・改善 | – 公開後の順位計測・効果測定 – レポーティング – 記事のリライト(改善)提案 |
依頼先の主な3つのタイプとそれぞれの特徴
SEO記事作成の依頼先は、大きく分けて3つのタイプが存在します。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の目的や予算に合わせて最適な依頼先を選ぶことが重要です。
| 依頼先のタイプ | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|---|
| ①記事作成代行会社 | – 品質が安定している – SEO戦略全体を相談できる – ディレクションの手間が少ない | – 費用が比較的高額 – 最低発注数などの制約がある場合も | – 品質と戦略性を重視したい – まとまった本数を継続的に依頼したい – 社内にディレクションリソースがない |
| ②クラウドソーシング | – 費用を抑えやすい – 1記事から気軽に依頼できる – 特定分野の専門家を探しやすい | – 品質にばらつきがある – ライター選定や管理の手間がかかる – コミュニケーションコストが高い | – 予算が限られている – 特定の記事だけ依頼したい – 社内にディレクションリソースがある |
| ③AIライティングツール | – スピードが圧倒的に速い – コストを大幅に削減できる – 大量の記事作成に対応できる | – 情報の正確性に欠ける場合がある – 独自性・専門性に乏しい – 最終的な編集・校正が必須 | – 記事の草案を効率的に作りたい – 大量の記事を低コストで作成したい – 編集・校正できる人材が社内にいる |
①記事作成代行会社(制作会社):品質と戦略性を重視するなら
専門の制作会社に依頼する最大のメリットは、品質の高さと安定性です。
経験豊富な編集者やディレクターが品質管理を行うため、質の高い記事を期待できます。
また、記事作成だけでなくSEO戦略全体を相談できるため、事業成果に直結するコンテンツ施策を展開したい企業に適しています。
一方で、ディレクターや管理者の人件費が含まれるため、費用は他の選択肢に比べて高くなる傾向があります。
しかし、その分コミュニケーションが円滑に進み、自社の手間を大幅に削減できるでしょう。
②クラウドソーシング(フリーランス):コストと柔軟性を求めるなら
クラウドソーシングサイトを利用すれば、フリーランスのライターに直接記事作成を依頼できます。
最大のメリットは、制作会社を介さないためコストを抑えられる点です。
また、特定の専門分野に精通したライターを直接探せるため、ニッチなジャンルの記事を依頼したい場合に有効です。
ただし、ライターのスキルや実績は玉石混交であり、品質にばらつきが出やすいのがデメリットです。
良いライターを見つけるための選定作業や、構成案の指示、納品物のチェックなど、自社でのディレクション業務が発生します。
③AIライティングツールの活用:スピードと量産を優先するなら
近年、AIライティングツールの進化は目覚ましく、記事作成の効率化に大きく貢献します。
キーワードを入れるだけで、数分で記事の草案を作成できるため、スピードとコスト削減の面で非常に強力です。
大量の記事を効率的に作成したい企業にとって、有効な選択肢となるでしょう。
しかし、AIが生成した文章は、情報の誤り(ハルシネーション)や著作権侵害のリスクを内包しています。
そのため、AIが作成した文章をそのまま公開するのは非常に危険です。
必ず人間の編集者がファクトチェックや校正、独自性の追加を行う「ハイブリッド型」の運用が前提となります。
【相場早見表】SEO記事作成の依頼にかかる費用は?料金体系別に徹底解説
記事作成を外注する上で、最も気になるのが費用ではないでしょうか。
費用は、依頼先のタイプや記事の専門性、品質によって大きく変動します。
ここでは、料金体系ごとの特徴と、具体的な費用相場を分かりやすく解説します。
自社の予算感と照らし合わせ、適正な価格を把握するための参考にしてください。
料金体系の種類(文字単価・記事単価・月額固定)
記事作成の料金体系は、主に以下の3つに分類されます。
それぞれの特徴を理解し、自社の発注計画に合ったものを選びましょう。
| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 文字単価制 | 1文字あたりの単価で費用が決まる最も一般的な形式。 | – 費用が分かりやすい – 文字数に応じて柔軟に調整できる | – 画像選定や入稿は別料金の場合が多い – 文字数を増やすと高額になる |
| 記事単価制 | 構成作成、執筆、画像選定などを含んだ1記事あたりの料金。 | – 1記事あたりの総額が明確 – オプションが少なく予算管理しやすい | – 文字数が少なくても費用は同じ – 修正回数に制限があることも |
| 月額固定制 | 毎月決まった本数の記事作成を依頼する契約形態。 | – 継続的な発注で単価が割安になる – 中長期的な施策に向いている | – 最低契約期間の縛りがある場合が多い – 月の依頼本数を消化できないと損になる |
品質レベル別・記事作成の費用相場
同じ文字数でも、記事の品質によって費用は大きく異なります。
安さだけで選ぶと、SEO効果が全く得られないばかりか、サイトの評価を下げることにもなりかねません。
品質と費用のバランスを見極めることが重要です。
| 品質レベル | 文字単価の目安 | 記事単価の目安 (5,000文字の場合) | 特徴・依頼先 |
|---|---|---|---|
| 標準品質 | 3円~5円 | 15,000円~25,000円 | – 経験のあるライターが執筆 – 基本的なSEO対策を実施 – 依頼先:クラウドソーシング、一部の制作会社 |
| 高品質 | 5円~10円 | 25,000円~50,000円 | – 専門分野の知見を持つライター – 競合分析に基づいた構成 – 編集者による校正あり – 依頼先:多くの制作会社 |
| 最高品質 | 10円以上 | 50,000円以上 | – 専門家や有資格者による執筆・監修 – 独自取材やデータ分析を含む – 戦略立案からサポート – 依頼先:専門特化型の制作会社 |
費用を抑えつつ品質を担保する3つのコツ
「コストは抑えたい、でも品質は妥協したくない」というのは、多くの担当者が抱える課題です。
ここでは、費用を抑えながらも、記事の品質を担保するための具体的なコツを3つご紹介します。
記事構成案を自社で用意する
記事作成の工程で最も重要なのが「構成案」です。
この構成案を自社で詳細に作成し、ライターには執筆のみを依頼することで、費用を抑えることが可能です。
キーワードや見出し、盛り込んでほしい内容などを具体的に指示しましょう。AIツールで草案を作成し、編集を依頼する
AIライティングツールで記事の草案(下書き)を作成し、プロのライターや編集者にリライトや校正を依頼する方法です。
ゼロから執筆してもらうよりも、工数が削減されるため費用を安く抑えられます。
品質を担保するために、SEOや編集スキルが高い人材に依頼することがポイントです。長期契約や発注本数をまとめて単価交渉する
制作会社に依頼する場合、単発での発注よりも、中長期的な契約やまとまった本数を発注することで、記事1本あたりの単価を交渉しやすくなります。
継続的なパートナーシップを築くことで、より柔軟な対応を期待できるでしょう。
【失敗しない】SEO記事作成の依頼先を選ぶ7つの重要ポイント
SEO施策の成果は、どのパートナーと組むかによって大きく左右されます。
しかし、数多くの代行会社やライターの中から、本当に信頼できる依頼先を見つけるのは容易ではありません。
ここでは、「外注で失敗したくない」担当者のために、依頼先を見極めるための7つの重要なチェックポイントを具体的に解説します。
| チェック項目 | 確認すべき具体的なポイント |
|---|---|
| 1. SEO実績 | – 検索順位や流入数、CV数などの数値データが伴う成功事例があるか – 自社と近しい業界での実績はあるか |
| 2. 専門性 | – 自社業界の専門知識を持つライターや編集者が在籍しているか – YMYL領域の場合、医師や弁護士など専門家の監修体制があるか |
| 3. 料金体系 | – 料金体系が明確で、見積もりの内訳が詳細か – オプション料金や追加費用について事前に説明があるか |
| 4. 品質管理 | – 編集者や校正者によるダブルチェック体制があるか – 専用ツールによるコピーコンテンツチェックを実施しているか |
| 5. コミュニケーション | – 担当者のレスポンスは迅速かつ丁寧か – 定例ミーティングなど、定期的な報告・相談の場があるか – 受け身ではなく、改善提案などをしてくれるか |
| 6. 契約内容 | – 納品物の著作権はどちらに帰属するかが明記されているか – 修正可能な回数や範囲が定められているか – 秘密保持契約(NDA)を締結できるか |
| 7. AI利用ポリシー | – AIライティングツールを使用しているか – 使用している場合、どの工程で、どの程度利用しているか – AI生成コンテンツに対する人間のチェック体制はどうなっているか |
1. SEO対策の実績と成功事例は具体的か
「SEOに強い」と謳う会社は多いですが、その根拠を確認することが重要です。
過去に手掛けた案件で、どのようなキーワードで検索順位を何位から何位に上げたのか、オーガニック流入やコンバージョンがどれだけ増加したのか、といった具体的な数値データを含む成功事例を提示してもらいましょう。
口頭での説明だけでなく、実際のレポートを見せてもらうのが理想です。
2. 自社業界・領域への専門性や知見はあるか(特にYMYL)
記事の品質は、書き手の専門知識に大きく依存します。
自社の業界や商材について深い知見を持つ依頼先を選ぶことで、読者にとって価値のある、専門的なコンテンツを作成できます。
特に、医療・健康・金融といったYMYL(Your Money or Your Life)領域の記事は、情報の正確性が検索順位に直結するため、医師や弁護士、FPといった有資格者による監修体制が整っているかどうかが極めて重要です。
3. 料金体系は明確で、費用対効果が見合っているか
見積もりを取る際は、料金の内訳を詳細に確認しましょう。
記事作成費用以外に、企画構成費、ディレクション費、画像選定費などのオプション料金が発生しないか、事前に確認することがトラブル防止に繋がります。
提示された費用でどのような成果が期待できるのか、費用対効果(ROI)の観点から慎重に検討しましょう。
4. 品質管理体制(編集・校正・コピーチェック)は整っているか
高品質な記事を安定的に納品してもらうためには、依頼先の品質管理体制の確認が不可欠です。
具体的には、以下のような点を確認しましょう。
- ライターが執筆した原稿を、別の編集者や校正者がチェックする体制があるか
- 誤字脱字や表記ゆれだけでなく、情報の正確性(ファクトチェック)も行っているか
- Copyscapeなどの専用ツールを使い、他サイトからの盗用や安易なリライトではないか(コピーコンテンツチェック)を確認しているか
5. コミュニケーションは円滑で、伴走してくれる姿勢があるか
外注は、依頼して終わりではありません。
成果を出すためには、依頼先と密に連携し、二人三脚で施策を進めていく必要があります。
担当者のレスポンスの速さや丁寧さはもちろん、自社のビジネスを理解し、より良くするための改善提案を積極的に行ってくれるような、パートナーとしての姿勢があるかを見極めましょう。
6. 契約内容(著作権の帰属、修正回数など)は明確か
契約前には、契約書の内容を隅々まで確認することが重要です。
特に以下の点は、後々のトラブルに発展しやすいため、必ず明確にしておきましょう。
- 著作権の帰属: 納品された記事の著作権は、発注元に譲渡されるのか。
- 修正回数: 無料で対応してくれる修正の回数や範囲はどこまでか。
- 秘密保持: 自社の機密情報を取り扱うため、秘密保持契約(NDA)を締結できるか。
7. AIライティングツールの使用ポリシーは開示されているか
AIツールの利用が一般化する中、依頼先がAIをどのように活用しているか、その方針を確認することも新たなチェックポイントです。
AIの利用自体が悪いわけではありませんが、その使い方によっては品質に大きな影響が出ます。
AIの使用有無や、使用している場合はどの工程でどの程度利用しているのか、そしてAIが生成した内容に対して人間がどのように関与し、品質を担保しているのか、透明性のある説明を求めましょう。
【目的別】おすすめSEO記事作成代行会社・サービスを比較
ここでは、数ある記事作成代行サービスを、企業の目的別に3つのカテゴリーに分類してご紹介します。
「戦略から一貫して任せたい」「専門性の高い高品質な記事が欲しい」「まずはコストを抑えて記事を量産したい」など、自社の状況やニーズに最も合った依頼先を見つけるための参考にしてください。
| 目的・ニーズ | おすすめの依頼先タイプ | 特徴 | 代表的なサービス例 |
|---|---|---|---|
| 戦略から任せたい | 戦略コンサルティング型 | – SEO戦略の立案から実行まで一気通貫で支援 – 事業成果(売上・リード獲得)へのコミット | テクロ株式会社、株式会社LANY |
| 品質を最優先したい | 高品質・専門特化型 | – 専門家監修などE-E-A-Tを重視 – YMYL領域やニッチなBtoBに強い | 株式会社ウィルゲート(EDITORU)、サクラサクマーケティング株式会社 |
| コストと量を重視したい | 量産・コスパ型 | – 低単価で大量の記事作成に対応 – AI活用やクラウドソーシングが中心 | ランサーズ、クラウドワークス、AI-SEO |
戦略コンサルティング型:事業成果にコミット
単に記事を制作するだけでなく、SEO戦略の立案から効果測定、改善提案までを一貫して支援してくれるのがこのタイプです。
Webマーケティング全体の視点から、どのようなコンテンツが事業成果(リード獲得や売上向上)に繋がるかを設計してくれます。
特にBtoBマーケティングに課題を抱える企業には、データに基づいた戦略と伴走型の支援を提供するテクロ株式会社などがおすすめです。豊富な支援実績から得られた知見を基に、顧客ごとに最適化された戦略を実行します。
高品質・専門特化型:E-E-A-Tを重視
コンテンツの「質」を何よりも重視し、情報の正確性や信頼性を追求するタイプです。
YMYL領域における専門家(医師、弁護士など)の監修や、BtoBのニッチな業界に精通したライター陣を抱えているのが特徴です。
Googleの品質評価基準であるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を最大限に高めたい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。
量産・コスパ型:記事数を重視
オウンドメディアの立ち上げ初期段階など、まずはサイト全体の情報量を増やすために記事数を確保したい場合に適しています。
クラウドソーシングサービスを活用して多数のライターに発注したり、AIライティングツールを駆使して効率的に記事を生成したりすることで、低コストでの量産を実現します。
ただし、品質管理やディレクションは自社で行う必要がある点に注意が必要です。
AIは使える?SEO記事作成におけるAIライティングツールの賢い活用法
「AIに記事作成を任せても大丈夫?」という疑問は、多くの担当者が抱くところでしょう。
結論から言うと、AIは非常に「使える」ツールですが、それには「賢い活用法」が不可欠です。
AIを単なる執筆者としてではなく、優秀なアシスタントとして捉えることで、品質を担保しながらコストと工数を大幅に削減できます。
主要AIライティングツールの比較と特徴
SEO記事作成に役立つAIツールは数多く存在します。
それぞれに特徴があるため、目的に合わせて選ぶことが重要です。
| ツール名 | SEO機能の充実度 | コンテンツ品質 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| AI Writer | ★★★★★ | ★★★★★ | 競合調査から記事生成、SEO最適化までワンストップ。人間味のある自然な文章が強み。 |
| SAKUBUN | ★★★★☆ | ★★★★☆ | SEOに強い構成案を自動生成。多様なテンプレートで様々なジャンルに対応。 |
| Transcope | ★★★★☆ | ★★★★☆ | SEO分析機能が充実。既存記事の改善提案やキーワード抽出が得意。 |
| EmmaTools | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 作成したコンテンツのSEO効果を測定・スコアリングし、改善点を可視化。 |
AIと人間ライターの効果的な協業プロセス
最も現実的で成果に繋がりやすいのが、AIと人間がそれぞれの得意分野を活かして協業するプロセスです。
これにより、品質と効率の両立が可能になります。
- AIが担当: キーワードに基づいた構成案の複数パターン出し、競合情報の調査・要約、記事本文の草案作成
- 人間が担当: 最適な構成案の決定、AIが作成した草案のファクトチェック、独自の見解や事例の追加(オリジナリティの付与)、文章表現の調整・校正、最終的な仕上げ
このプロセスにより、人間はより創造的な作業に集中でき、記事の品質を飛躍的に高めることができます。
注意点:AIコンテンツの課題(ハルシネーション・著作権)と対策
AIの活用には、メリットだけでなく注意すべきリスクも存在します。
これらのリスクを理解し、対策を講じることが信頼性の高いコンテンツ作りに繋がります。
- ハルシネーション(もっともらしい嘘): AIは、事実ではない情報を事実であるかのように生成することがあります。特に専門的な内容や最新情報については、必ず信頼できる情報源(一次情報など)と照合し、ファクトチェックを徹底する必要があります。
- 著作権侵害: AIは学習データに含まれる既存のコンテンツと類似した文章を生成する可能性があります。意図せず著作権を侵害してしまうリスクを避けるため、Copyscapeなどのコピーチェックツールで必ず確認しましょう。
依頼前に知っておきたい!成果を出すためのSEO記事作成の基本
記事作成を外注先に「丸投げ」してしまうと、期待した成果は得られません。
依頼側である担当者も、SEO記事作成の基本的な知識を持つことで、依頼先とのコミュニケーションが円滑になり、納品物の品質を正しく評価できるようになります。
ここでは、成果を出すために最低限押さえておきたい3つの基本ポイントを解説します。
検索意図の理解とキーワード選定
SEO対策の出発点は、ユーザーの「検索意図」を深く理解することです。
ユーザーがそのキーワードで検索する時、何を知りたいのか、どんな課題を解決したいのかを徹底的に考え抜く必要があります。
例えば、「SEO 対策 費用」と検索する人は、単に料金を知りたいだけでなく、「自分の予算でどこまでできるのか」「費用対効果は合うのか」といった潜在的なニーズを抱えています。この意図に応えることが、読者の満足度を高め、上位表示に繋がります。
読者と検索エンジンに評価される記事構成の作り方
記事の品質は、その骨格となる「構成」で8割決まると言っても過言ではありません。
良い構成とは、読者の疑問や悩みが、論理的な順序で解決されていくストーリーになっています。
H1(大見出し)で記事の全体像を示し、H2、H3(中・小見出し)で具体的な内容を深掘りしていく階層構造は、読者と検索エンジンの双方にとって内容を理解しやすくします。この構成案の質が、記事全体の質を大きく左右します。
Googleが重視する「E-E-A-T」とは?品質を高める4要素
現在のGoogleは、コンテンツの品質を評価する上で「E-E-A-T」という基準を非常に重視しています。
これは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼性)の頭文字を取ったものです。
| E-E-A-T | 意味 | 具体的な対策例 |
|---|---|---|
| Experience (経験) | そのトピックに関する実体験や一次情報 | – 実際に商品やサービスを使用したレビュー – 独自に行ったアンケート調査の結果 |
| Expertise (専門性) | その分野に関する深い知識やスキル | – 専門用語の分かりやすい解説 – 網羅的で詳細な情報提供 |
| Authoritativeness (権威性) | その分野の第一人者として認められているか | – 著者情報(プロフィール)の明記 – 公的機関や権威あるサイトからの被リンク |
| Trust (信頼性) | 情報が正確で信頼できるか | – 専門家による記事の監修 – 信頼できる情報源(論文、公的データ)の引用 |
これらの要素を記事に盛り込むことで、Googleからの評価を高めることができます。
外注を成功に導く!依頼から記事公開までの具体的な6ステップ
「何から始めればいいのかわからない」という方のために、SEO記事作成の外注を成功させるための具体的なプロセスを6つのステップに分けて解説します。
この流れに沿って進めることで、抜け漏れなく、スムーズにプロジェクトを進行できます。
ステップ1:RFP(提案依頼書)の作成と問い合わせ
まずは、自社の目的、課題、予算、要望などをまとめた「RFP(提案依頼書)」を作成します。
これを基に複数の依頼先候補に問い合わせることで、各社の提案を同じ土俵で比較検討できます。
RFPに記載すべき項目には、サイトURL、ターゲット読者、目的(リード獲得、ブランディングなど)、希望記事数、予算感などがあります。
ステップ2:ヒアリングと依頼先の選定・契約
RFPを送付したら、各社とヒアリング(打ち合わせ)の機会を持ちます。
この場で、実績や品質管理体制、コミュニケーション方法などを詳しく確認し、最も信頼できるパートナーを選定します。
契約に進む際は、前述の「契約内容のチェックポイント」を参考に、契約書の内容を十分に確認しましょう。
ステップ3:キックオフMTGと構成案のすり合わせ
契約後は、プロジェクトを円滑に始動させるためのキックオフミーティングを実施します。
ここで、記事の方向性、ペルソナ、トンマナなどを依頼先と共有し、認識を合わせます。
特に最初の数記事は、構成案の段階で詳細にすり合わせを行うことが、手戻りを防ぎ、意図通りの記事を制作する上で非常に重要です。
ステップ4:執筆と初稿の確認・フィードバック
依頼先から初稿が納品されたら、内容を確認します。
構成案に沿っているか、レギュレーションは守られているか、情報の正確性は担保されているかなどをチェックしましょう。
修正を依頼する際は、単に「修正してください」ではなく、「ここの表現は、ターゲット読者にはより平易なこちらの言葉の方が伝わりやすいです」のように、具体的かつ建設的なフィードバックを心がけることが品質向上に繋がります。
ステップ5:修正対応と最終稿の納品
フィードバックを基に、依頼先が記事を修正します。
修正稿が上がってきたら再度確認し、問題がなければ校了となり、最終的な原稿が納品されます。
この段階で、コピーチェックツールを使って独自性を最終確認しておくと、より安心です。
ステップ6:記事公開と効果測定・改善
記事は公開して終わりではありません。
むしろ、公開してからがスタートです。
Google AnalyticsやSearch Consoleといったツールを使い、公開後の検索順位や流入数、滞在時間などを定期的に測定します。
そして、そのデータを基に、より成果を高めるためのリライト(改善)を継続的に行うことが、SEOで成功するための鍵となります。
SEO記事作成の依頼に関するよくある質問(Q&A)
最後に、記事作成の外注に関して、担当者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 最低何記事から依頼できますか?
A1. 依頼先によって大きく異なります。制作会社の場合は、最低5本〜10本程度のまとまった発注や、3ヶ月以上の契約期間が条件となることが多いです。一方、クラウドソーシングでは1記事から気軽に依頼することが可能です。まずは1記事をテストとして依頼し、品質や相性を確認できるか相談してみるのがおすすめです。
Q2. 成果が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A2. SEOは即効性のある施策ではなく、中長期的な視点が必要です。一般的には、記事を公開してからGoogleに評価され、成果(検索順位の上昇や流入増加)を実感できるまでには、最低でも3ヶ月〜半年、場合によっては1年以上かかることもあります。サイトの現状や競合の強さによって期間は変動するため、焦らず継続的に取り組むことが重要です。
Q3. 納品された記事の著作権はどうなりますか?
A3. 契約内容によりますが、一般的には、検収が完了し報酬の支払いが済んだ時点で、記事の著作権は発注元に譲渡されるケースがほとんどです。ただし、トラブルを避けるため、契約書に「著作権は発注者に譲渡される」という旨の条項が明記されているかを必ず確認してください。
Q4. 記事で使う画像の選定や作成も依頼できますか?
A4. 多くの制作会社では、オプションサービスとして対応可能です。フリー素材の中から記事内容に合った画像を選定するだけでなく、オリジナルの図解やインフォグラフィックを作成してくれる会社もあります。画像の有無は読者の理解度や滞在時間に大きく影響するため、必要に応じて依頼を検討しましょう。もちろん、追加費用が発生する場合がほとんどなので、料金と合わせて確認が必要です。
まとめ:戦略的な記事作成の外注で、事業成長を加速させよう
本記事では、SEO記事作成を外注する際の費用相場から、失敗しない依頼先の選び方、具体的な進行ステップまでを網羅的に解説しました。
重要なのは、記事作成の外注を単なる「作業の委託」と捉えるのではなく、専門家の知見を活用して事業成果を最大化するための「戦略的投資」と考えることです。
社内のリソース不足やノウハウ不足といった課題を解決し、本来注力すべきコア業務に集中するためにも、信頼できるパートナーとの連携は不可欠です。
この記事で紹介したポイントを参考に、まずは自社の課題を整理し、複数の依頼先に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
私たちテクロ株式会社では、BtoBマーケティングに特化したデータドリブンなコンテンツ戦略で、100社以上の企業様のリード獲得と事業成長に貢献してきました。
もし、SEO記事作成やオウンドメディア運用にお困りでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
なお、テクロ株式会社では「SEOのキーワード選定マニュアル」を無料で配布しています。
オウンドメディアで上位表示を獲得したいBtoB企業様はぜひご確認ください。
「SEOのキーワード選定マニュアル」をチェック!

- キーワード選定とは
- キーワード選定前に行うこと
- キーワード選定の手順
- キーワード選定の注意点
- おすすめのツール
BtoB企業様のオウンドメディアで実施しているテクロのキーワード選定の方法を公開しています。「SEOのキーワード選定マニュアル」をお気軽にダウンロードください。
SEO記事の評価を高めるには他に何をすべきですか?
記事の執筆以外には、内部対策として画像やリンクの適切な設置、クローラーの巡回頻度を増やす対策、ユーザーの意識を高めるコンテンツ設計が効果的です。これらを組み合わせて、より高い評価を得ることが可能です。
SEO向けの記事作成時に注意すべきポイントは何ですか?
記事作成時には、他社サイトとの類似度に注意し、コピペを避けること、不要な情報を排除し、ユーザーニーズに合った適切な内容を提供することが重要です。また、最新の情報を掲載し、文章の校正も欠かさないことが求められます。
文字数や記事数はSEOにどう影響しますか?
文字数や記事数は直接的にランキングに影響しません。重要なのは、記事の質と情報の充実度であり、適切な文字数と継続的なコンテンツ更新がサイト全体の評価を向上させます。
効果的なSEO記事の特徴は何ですか?
効果的なSEO記事は、ユーザーの検索ニーズを満たし、情報を網羅し、E-E-A-Tの基準を意識した内容であることが特徴です。対象キーワードの選定や競合サイトの分析、構成の工夫、本文の質の向上が重要です。
SEO記事とは何ですか?
SEO記事とは、検索エンジンの上位に表示されることを目的として作成されるコンテンツであり、自社の商品やサービスに関する情報を通じて顧客を獲得し、売上を増やすことを目指しています。