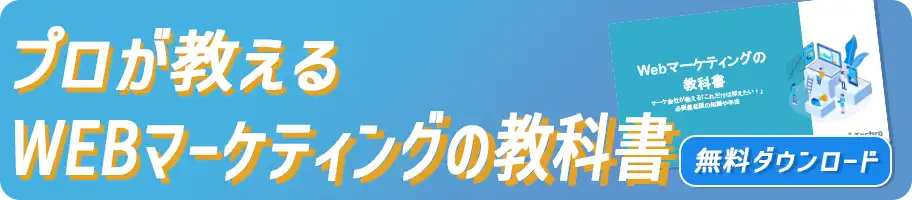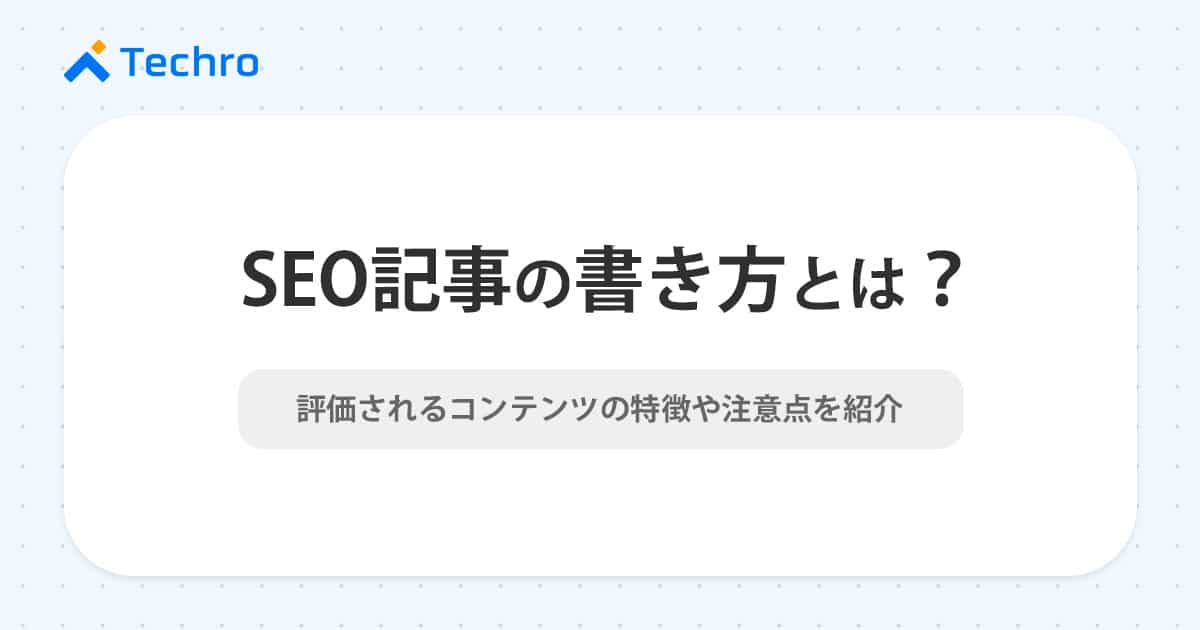オウンドメディアの目的とは?成功に導く4つの役割と始め方を徹底解説
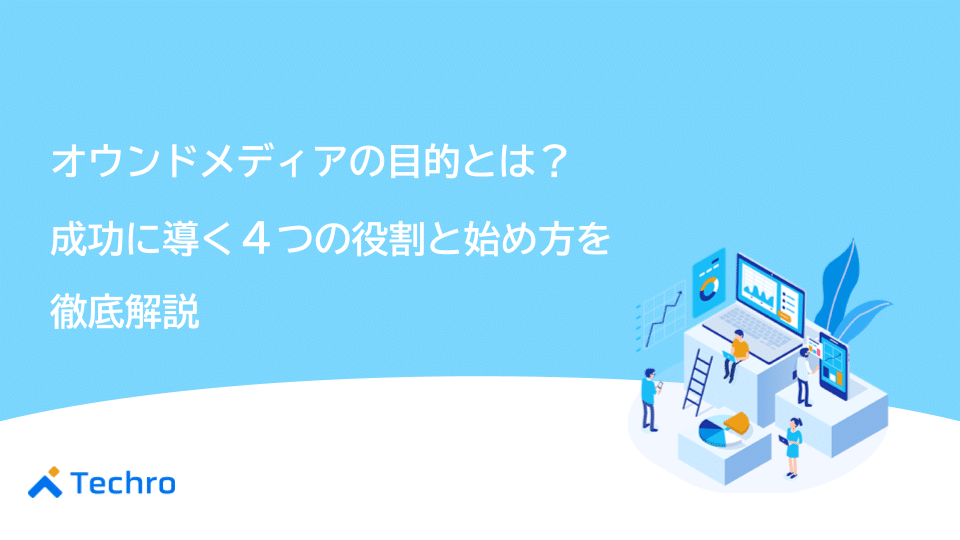
- 「自社の集客力を高めたいけれど、広告費はどんどん高くなるばかり…」
- 「会社の魅力を伝えたいのに、求人サイトだけでは伝わりきらない」
- 「将来のために、安定したマーケティング基盤を築きたい」
このようなお悩みを抱える企業のマーケティング担当者や経営者の方にとって、「オウンドメディア」は非常に強力な解決策となり得ます。
しかし、ただやみくもに始めても「時間とコストをかけたのに意味がなかった」という結果に陥りかねません。
成功の鍵は、オウンドメディアを「何のためにやるのか」という目的を明確にすることです。
この記事では、
- オウンドメディアの基本的な役割
- 具体的な4つの目的
- 導入のメリット・デメリット
- 成功に導くための始め方
までを徹底的に解説します。
最後まで読めば、あなたの会社がオウンドメディアを始めるべきか、そして、どのように進めれば事業成長に繋がるのかが明確になるはずです。
なお、テクロ株式会社では「オウンドメディア作成マニュアル」資料を無料で配布しています。
マーケティング会社が実践しているオウンドメディアの作り方を知りたいBtoB企業様は、ぜひご確認ください。
「オウンドメディア作成マニュアル」をチェック!

- オウンドメディアの基礎知識
- 担当者が抱えるオウンドメディアの課題
- オウンドメディアを作る手順
- オウンドメディアを作るにあたって大切なこと
オウンドメディアの基本から立ち上げまでの手順を解説しています。「オウンドメディア作成マニュアル」をお気軽にダウンロードください。
目次
そもそもオウンドメディアとは?基本をわかりやすく解説

本格的な目的の話に入る前に、まずは「オウンドメディア」の基本を整理しましょう。
言葉は知っていても、ホームページやブログとの違いを正確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。
ここでは、基本的な定義やマーケティングにおける役割をわかりやすく解説します。
オウンドメディアの定義とトリプルメディアにおける役割
オウンドメディアとは、企業が自社で所有し、管理・運営するメディア全般を指します。
Webサイトだけでなく、広義にはパンフレットや広報誌なども含まれますが、一般的には企業ブログやWebマガジンなどを指すことが多いです。
このオウンドメディアを理解する上で欠かせないのが、「トリプルメディア」という考え方です。
トリプルメディアは、企業が利用するメディアを以下の3つに分類したフレームワークです。
| 用語 | 読み | 意味 |
|---|---|---|
| オウンドメディア《Owned Media》 | おうんどめでぃあ | 自社で所有するメディア。企業ブログ、公式サイト、メルマガなど。 |
| ペイドメディア《Paid Media》 | ぺいどめでぃあ | 費用を支払って利用する広告メディア。テレビCM、リスティング広告、SNS広告など。 |
| アーンドメディア《Earned Media》 | あーんどめでぃあ | 生活者や第三者が情報発信するメディア。SNSでの口コミ、レビューサイト、ニュース記事など。 |
オウンドメディアは、これら3つの中で情報発信の中核を担う「ハブ」のような存在です。
ペイドメディアで集めた注目をオウンドメディアに誘導し、そこで価値ある情報を提供することでアーンドメディアでの拡散(口コミ)を生み出す、という好循環を作ることができます。
ホームページやブログ、SNSとの違いは?
オウンドメディアと聞くと、「ホームページやブログ、SNSと何が違うの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
これらの違いは、主に「目的」と「役割」にあります。
以下の表でそれぞれの違いを整理してみましょう。
| 種類 | 主な目的 | 主なコンテンツ内容 |
|---|---|---|
| オウンドメディア | 見込み顧客の獲得・育成、ブランディング、採用強化など戦略的な目的 | 読者の課題解決記事、導入事例、専門知識の解説、社員インタビューなど |
| ホームページ(コーポレートサイト) | 企業情報の発信、信頼性の担保 | 会社概要、事業内容、プレスリリース、IR情報など |
| 企業ブログ | 情報発信、ファンとの交流 | 専門分野のノウハウ、業界ニュース、イベントレポート、社内の日常など |
| 企業SNS | 認知拡大、ファンとの交流、リアルタイムな情報発信 | 新製品情報、キャンペーン告知、ユーザーとのコミュニケーションなど |
このように、ホームページは企業の「名刺」のような役割、SNSは「リアルタイムな交流の場」としての役割が強いです。
一方、オウンドメディアはこれらを包括し、読者の課題解決を通じて信頼関係を築き、最終的に事業目標の達成を目指す、より戦略的なメディアであると言えます。
関連記事:オウンドメディアの意味とは?役割とスムーズな運用方法を紹介
オウンドメディア運営の4つの主要目的

オウンドメディアの基本を理解したところで、いよいよ本題である「運営の目的」について見ていきましょう。
企業がオウンドメディアを運営する目的は多岐にわたりますが、主に以下の4つに集約されます。
自社の課題がどれに当てはまるか考えながら読み進めてみてください。
- 目的①:潜在層にアプローチし「集客」する
- 目的②:企業の想いを伝え「ブランディング」を強化する
- 目的③:顧客育成を行い「売上向上」に貢献する
- 目的④:自社の魅力を発信し「採用活動(リクルーティング)」を促進する
目的①:潜在層にアプローチし「集客」する
オウンドメディアの最も大きな目的の一つが、見込み顧客の集客です。
特に、自社の製品やサービスをまだ知らない「潜在層」へのアプローチに効果を発揮します。
ユーザーが抱える悩みや疑問に対し、解決策となるような質の高い記事(コンテンツ)を制作し、検索エンジン経由でのサイト流入を狙います。
例えば、「BtoB マーケティング 手法」と検索したユーザーに対して、様々な手法を解説する記事を提供することで、自社の存在を認知してもらうきっかけになります。
これは、一度作成したコンテンツが資産としてインターネット上に残り続け、継続的に集客してくれるため、「資産型」の集客モデルと言えます。
広告のように費用をかけ続けないと効果が途切れる心配がないのが大きな強みです。
目的②:企業の想いを伝え「ブランディング」を強化する
オウンドメディアは、企業のブランドイメージを構築・強化するための強力なツールです。
広告の短い時間や限られたスペースでは伝えきれない、企業の理念やビジョン、製品開発の裏側にあるストーリーなどを深く伝えることができます。
専門知識やノウハウをまとめたコラム記事を発信すれば、その分野の専門家としての権威性を示すことができます。
また、企業の価値観や文化を発信することで、それに共感するファンを育て、長期的な顧客ロイヤルティの向上に繋げることが可能です。
他のメディアと違い、発信する情報の内容やトーンを完全に自社でコントロールできるため、意図した通りのブランディングを実現しやすいのが特徴です。
目的③:顧客育成を行い「売上向上」に貢献する
オウンドメディアは、単に人を集めるだけでなく、集めた見込み顧客を育成し、最終的な購買や契約に繋げる「リードナーチャリング」の役割も担います。
リードナーチャリングとは、見込み顧客と継続的にコミュニケーションを取り、購買意欲を高めていく活動のことです。
例えば、以下のような流れで売上向上に貢献します。
- 認知・興味関心
- 課題解決コンテンツで潜在顧客を集客する。
- 情報収集・比較検討
- 製品の活用法や導入事例の記事を読んでもらい、理解を深めてもらう。
- コンバージョン
- ホワイトペーパー(お役立ち資料)のダウンロードや、セミナー申し込み、問い合わせに繋げる。
このように、顧客の検討段階に合わせたコンテンツを提供することで、自然な形で購買プロセスを進めてもらい、売上向上を実現します。
目的④:自社の魅力を発信し「採用活動(リクルーティング)」を促進する
近年、採用活動におけるオウンドメディアの重要性が高まっています。
これは「オウンドメディアリクルーティング」とも呼ばれ、多くの企業が取り入れています。
求人サイトに掲載されている情報だけでは、給与や待遇といった条件面での比較になりがちです。
しかし、オウンドメディアを使えば、以下のような多角的な情報を発信できます。
- 活躍する社員のインタビュー
- 日々の業務内容やプロジェクトの裏側
- 独自の社内制度や企業文化の紹介
- 経営陣が語る事業のビジョンや想い
これらの情報を発信することで、求職者はその企業で働くイメージを具体的に持つことができます。
結果として、企業の価値観に共感し、カルチャーにマッチした優秀な人材からの応募が増え、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
なぜ目的設定が重要?「意味ない」投資にしないための第一歩
ここまで4つの主要な目的を解説してきましたが、なぜこれほどまでに目的設定が重要なのでしょうか。
それは、目的が曖昧なままオウンドメディアを始めると、ほぼ確実に失敗するからです。
- 誰に何を伝えたいのかがブレてしまい、コンテンツの方向性が定まらない。
- 成果を測る指標(KPI)が不明確で、施策の良し悪しを判断できない。
- 成果が見えにくいため、社内の協力が得られず、モチベーションも維持できない。
結果として、「時間とコストをかけたのに効果がなかった」「意味ない投資だった」という結論に陥ってしまいます。
そうならないためにも、オウンドメディアを立ち上げる前に「誰の、どんな課題を解決するために、何を達成するのか」という目的を明確に定義することが、成功への第一歩となるのです。
目的を明確にするSMARTな目標設定の具体例
効果的な目標を設定するためには、「SMART」というフレームワークが役立ちます。
これは、目標を以下の5つの要素で具体的かつ測定可能にする考え方です。
| 要素 | 英語 | 意味 |
|---|---|---|
| S | Specific | 具体的でわかりやすいか |
| M | Measurable | 測定可能か(数値で測れるか) |
| A | Achievable | 達成可能か |
| R | Relevant | 関連性があるか(事業目標と連動しているか) |
| T | Time-bound | 期限が明確か |
実際に、先ほど紹介した4つの目的に対して、SMARTを用いた目標設定の例を見てみましょう。
| 目的 | 悪い目標例 | SMARTな目標例 |
|---|---|---|
| 集客 | サイトへのアクセスを増やす | 1年後に、SEO経由の月間アクセス数を10万PVにする |
| ブランディング | 会社の認知度を上げる | 半年後に、社名での指名検索数を現状の2倍にする |
| 売上向上 | 問い合わせを増やす | 1年後に、オウンドメディア経由の月間問い合わせ件数を20件にする |
| 採用 | 良い人材からの応募を増やす | 次の採用期間終了までに、オウンドメディア経由の応募者数を10名獲得する |
このように、具体的で測定可能な目標を立てることで、チーム全員が同じ方向を向いて施策を進められるようになります。
【稟議にも使える】オウンドメディアのメリット・デメリットを徹底比較

オウンドメディアの導入を社内で提案する際には、良い面だけでなく、課題となる可能性のある面も客観的に示すことが重要です。
ここでは、導入を判断するための材料として、オウンドメディアのメリットとデメリットを詳しく解説します。
オウンドメディアを運営する5つの大きなメリット
まずは、オウンドメディアがもたらす大きなメリットを5つご紹介します。
これらは、広告などの短期的な施策では得られない、中長期的な価値となります。
メリット①:広告費に依存しない資産型の集客が可能になる
最大のメリットは、広告費をかけ続けなくても、継続的に集客できる仕組みを構築できる点です。
一度作成した質の高いコンテンツは、検索エンジンを通じて半永久的にユーザーをサイトに呼び込み続けます。
これは、Web上に「資産」を構築していくようなもので、長期的にはコストパフォーマンスが非常に高くなります。
メリット②:コンテンツを二次利用しマーケティング活動を効率化できる
オウンドメディアで作成したコンテンツは、一度きりで終わりではありません。
以下のように、様々な形で二次利用できます。
- 記事の内容を要約してメルマガで配信する
- 記事の図解や要点をSNSで発信する
- 複数の関連記事をまとめて「ホワイトペーパー(資料)」を作成する
- 記事の内容を営業資料やセミナーに活用する
このように、一つのコンテンツを多角的に活用することで、マーケティング活動全体を効率化できます。
メリット③:自社で情報をコントロールし正確なブランディングができる
オウンドメディアは自社で完全に管理できるため、伝えたいメッセージを、伝えたい形で、伝えたいタイミングで発信できます。
広告のような文字数制限や、他のメディアのような第三者の解釈を挟むことなく、企業の理念やブランドの世界観を正確に表現することが可能です。
これにより、一貫性のあるブランディングを実現できます。
メリット④:顧客データを蓄積・分析し、事業改善に活かせる
オウンドメディアを運営すると、Google Analyticsなどのツールを使って、読者の行動データを詳細に分析できます。
- どの記事がよく読まれているのか?
- どのようなキーワードで検索して訪れているのか?
- どのページで離脱しているのか?
これらのデータは、顧客が何に悩み、何に関心を持っているかを示す貴重な情報源です。
顧客理解を深めることで、コンテンツの改善はもちろん、商品開発やサービス向上にも繋げることができます。
メリット⑤:採用ミスマッチを防ぎ、採用コストを削減できる
採用目的で運営する場合、企業のリアルな姿を伝えることで、求職者は入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。
これにより、自社の文化や価値観に本当にマッチする人材からの応募が集まりやすくなり、採用のミスマッチが減少します。
ミスマッチが減ることは、早期離職の防止に繋がり、結果として採用や教育にかかるトータルコストの削減に貢献します。
知っておくべき3つのデメリットと対策
次に、導入前に必ず理解しておくべきデメリットと、その対策について解説します。
課題を事前に把握しておくことで、計画的かつ着実なメディア運営が可能になります。
デメリット①:成果が出るまでに時間がかかる
オウンドメディアは、種をまいてから収穫するまでに時間がかかる農作業に似ています。
コンテンツが検索エンジンに評価され、安定したアクセスが集まるようになるまでには、一般的に最低でも半年から1年程度の期間が必要です。
短期的な成果を求めず、中長期的な視点で計画を立てることが重要です。最初の半年間はアクセス数よりも「コンテンツの本数」や「キーワード順位」といったプロセス指標を追いかけるなど、段階的なKPIを設定しましょう。
デメリット②:継続的なコンテンツ制作のコスト・リソースが必要
質の高いコンテンツを定期的に制作・更新し続けるためには、相応の人的リソースとコストがかかります。
企画、取材、執筆、編集、デザイン、公開作業など、多くの工数が必要です。
まずは社内のリソースを洗い出し、誰がどの役割を担うのかを明確にした上で、無理のない更新頻度を決めましょう。社内に専門知識を持つ人材がいない場合やリソースが不足している場合は、コンテンツ制作を外部の専門会社に委託するのも有効な選択肢です。
デメリット③:運用ノウハウがないと成果に繋がらない
ただやみくもに記事を書き続けても、成果に繋げるのは難しいのが現実です。
オウンドメディアで成果を出すためには、以下のような専門的なノウハウが求められます。
SEO(検索エンジン最適化)の知識
コンテンツマーケティングの戦略設計
データ分析に基づいた改善スキル
社内にこれらのノウハウを持つ人材がいない場合は、育成に時間を投資するか、立ち上げ初期から専門の運用代行会社やコンサルタントに相談するのが成功への近道です。外部の知見を活用することで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。
関連記事:オウンドメディア運用代行10選を徹底比較!メリットやサービス内容も紹介
オウンドメディアのデメリット

オウンドメディアは、企業にとって大きなメリットをもたらす一方で、以下のようないくつかのデメリットもあります。
- 立ち上げ時には一定の初期コストと工数が必要
- 効果が表れるまでには時間がかかる
- コンテンツの定期的な更新が不可欠
- 自社でのコンテンツ制作には人的リソースの確保が必要
オウンドメディアを成功に導くためには、これらのデメリットを理解し、適切に対処していくことが重要です。
オウンドメディア運用におけるデメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。
立ち上げ時には一定の初期コストと工数が必要
オウンドメディアを立ち上げる際には、一定の初期コストと工数が必要になることを認識しておくべきです。
まず、メディアのコンセプト作りから始まり、対象とする商材やターゲットオーディエンスの選定、記事の企画立案など、戦略的な準備に時間を要します。
また、メディア運営に必要な人材の確保やチームの編成、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)やMA(マーケティング・オートメーション)ツールの導入なども欠かせません。
これらの初期設定には、ある程度の予算と社内リソースの投資が必要となるでしょう。
オウンドメディアの立ち上げを検討する際は、短期的なコストではなく、中長期的な運用体制やランニングコストについて見積もっておくことが賢明です。
初期投資を十分に行い、しっかりとした基盤を整えることが、オウンドメディアの成功への第一歩となります。
効果が表れるまでには時間がかかる
オウンドメディアを立ち上げても、すぐに目に見える成果が表れるわけではありません。
特に、SEOの効果を実感するまでには、ある程度の時間を要します。
新しいサイトがGoogleにインデックスされ、検索結果の上位に表示されるようになるまでには、通常数ヶ月から半年程度かかると言われています。
また、オウンドメディアの認知度を高め、ユーザーからの信頼を獲得するためには、継続的で価値のあるコンテンツの提供が不可欠です。
一定の記事数や読者数を確保するまでには、長期的な取り組みが必要となるでしょう。
オウンドメディアの運営には、短期的な成果よりも中長期的な視点が重要です。
効果が表れるまでには時間がかかることを理解し、一貫性のある情報発信を続けていく姿勢が求められます。
じっくりと腰を据えて取り組むことが、オウンドメディアの成功につながるのです
コンテンツの定期的な更新が不可欠
オウンドメディアを運営するうえで、コンテンツの定期的な更新は欠かせません。
読者に新鮮で価値ある情報を提供し続けることが、オウンドメディアの存在価値を高めるためには重要だからです。
サイトが更新されていないと、読者は次第に離れていってしまうでしょう。
また、検索エンジンのアルゴリズムも定期的に更新されるサイトを高く評価する傾向にあります。
オウンドメディアを運営する際は、適切な更新頻度を維持することが求められます。
その際、単に記事を量産するだけではなく、読者のニーズや関心に合致したテーマ選びが大切です。
トレンドを捉えたタイムリーな話題提供や独自の視点に基づく深掘りした情報発信など、質の高いコンテンツ制作を心がける必要があります。
定期的かつ戦略的なコンテンツ更新がオウンドメディアの持続的な成長につながるのです。
自社でのコンテンツ制作には人的リソースの確保が必要
オウンドメディアのコンテンツ制作を自社で行う場合、社内の人的リソースの確保が重要な課題となります。
質の高い記事を定期的に発信していくためには、専任のライターやエディター、ディレクターといった人材が必要不可欠です。
しかし、社内の人手が限られている企業では、既存業務とオウンドメディアの運営を並行して行うことが難しいかもしれません。
その場合、外部のライターやクリエイターに委託することも一つの選択肢です。
ただし、自社の商材やサービスに精通した社員が制作に関わることで、より自社の強みを活かしたオリジナリティのあるコンテンツが生み出せる可能性が高まります。
オウンドメディアの運営には、一定の人的コストがかかることを念頭に置き、社内外の適切なリソース配分を検討することが肝要です。
戦略的なコンテンツ制作体制の構築がオウンドメディアの成功に向けた鍵となるでしょう。
また、以下の記事ではオウンドメディア運営に欠かせない効果的な運営戦略について詳しく解説しているため、参考にしてみましょう。
関連記事:オウンドメディアの戦略の立て方とは?手順や成功のポイントを紹介
【目的別】オウンドメディアの成功事例3選

理論だけでなく、実際の成功事例を見ることで、自社でオウンドメディアを運営するイメージがより具体的になります。
ここでは、目的別に3つの優れた成功事例を紹介します。
【採用目的】企業の文化を伝え、優秀な人材獲得に成功した事例
トヨタ自動車株式会社:「トヨタイムズ」
日本を代表する企業であるトヨタ自動車が運営する「トヨタイムズ」は、採用ブランディングの好事例です。
社長自身が編集長として登場し、会社の未来や課題について赤裸々に語るコンテンツは大きな話題を呼びました。
他にも、現場で働く社員の想いや、製品開発の裏側など、従来の広報では伝えきれなかった情報を発信しています。
これにより、「世界をリードする巨大企業」というイメージだけでなく、「変革に挑戦し続ける人間味あふれる企業」という新たなブランドイメージを構築し、未来のトヨタを担う多様な人材の獲得に繋げています。
【リード獲得目的】BtoBで月間132万PV、資料DL168件を達成した事例
株式会社サムシングファン:オウンドメディア「映像活用ノウハウ”DOOONUTSS”」
動画活用サービスを提供する株式会社サムシングファンは、オウンドメディア運用によってリード獲得に大きく成功したBtoB企業の事例です。
弊社テクロ株式会社が支援し、「動画制作」や「映像活用」に関連するキーワードで質の高いコンテンツを制作し続けました。
その結果、月間PV数は1.5万から132万PVに、月間の資料ダウンロード数は0件から168件へと劇的に増加しました。
ターゲット顧客の課題に寄り添った情報提供が、見込み顧客からの信頼獲得とコンバージョンに直結した好例です。
【認知拡大目的】新たなターゲット層を開拓し流入数4.75倍を達成した事例
株式会社アジャイルウェア:オウンドメディア「Kiitela(キイテラ)」
プロジェクト管理ツールなどを提供する株式会社アジャイルウェアは、新たなターゲット層への認知拡大を目的としてオウンドメディアを立ち上げました。
こちらも弊社テクロが支援し、従来のターゲットとは異なる層が持つであろう課題を起点にコンテンツを企画・制作しました。
ターゲットのニーズに合わせたコンテンツ発信やSNSでの拡散施策の結果、サイトへの流入数は4.75倍に増加し、これまでリーチできていなかった新たな顧客層からのサービス利用に繋がりました。
オウンドメディアが事業拡大の新たなきっかけを作った事例と言えます。
目的達成に導く!オウンドメディアの始め方5ステップ
成功事例を見て、いよいよ自社でも始めてみたいという気持ちが高まってきたのではないでしょうか。
ここでは、計画倒れになることなく、着実に成果を出すためのオウンドメディアの始め方を5つのステップで解説します。
ステップ1:オウンドメディアの「目的」と「KGI」を明確にする
最初に戻りますが、やはり最も重要なのが「目的」の明確化です。
自社の事業課題(売上、集客、採用など)を洗い出し、オウンドメディアを通じて何を最終的に達成したいのか、KGI《Key Goal Indicator》(重要目標達成指標)を決定します。
- 例: 事業課題が「新規顧客からの売上低迷」であれば、KGIは「オウンドメディア経由の年間受注金額 1,200万円」など。
このKGIが、メディア運営全体の北極星となります。
ステップ2:ターゲットとなる「ペルソナ」を具体的に設計する
次に、「誰に」情報を届けるのかを具体的に定義します。
そのために有効なのが「ペルソナ」の設定です。
ペルソナとは、自社の理想的な顧客像を、具体的な一人の人物のように詳細に設定したものです。
BtoB企業の場合、以下のような項目を設定します。
- 基本情報: 年齢、性別、役職
- 企業情報: 業界、企業規模
- 業務内容: 担当業務、役割、責任範囲
- 課題・ニーズ: 業務上の悩み、達成したい目標
- 情報収集の方法: よく見るWebサイト、利用するSNS
ペルソナを具体的に描くことで、チーム内でのターゲット像の認識が統一され、コンテンツの企画や表現がブレにくくなります。
ステップ3:目的達成度を測る「KPI」を設定する
KGIという最終ゴールにたどり着くための中間指標として、KPI《Key Performance Indicator》(重要業績評価指標)を設定します。
KPIを定期的に観測することで、施策が順調に進んでいるか、改善が必要かを判断できます。
KPIは、オウンドメディアの目的によって異なります。
| 目的 | KPIの例 |
|---|---|
| 集客 | PV数、UU数、検索順位、自然検索流入数 |
| ブランディング | 指名検索数、記事のSNSシェア数、サイテーション数 |
| 売上向上 | CVR(コンバージョン率)、CPA(顧客獲得単価)、資料請求件数 |
| 採用 | 応募数、採用イベント申込数、採用ページのPV数 |
ステップ4:コンテンツ制作と運用の「体制」を構築する
オウンドメディアを継続的に運営していくための体制を整えます。
最低でも、以下のような役割が必要です。
- 編集長/ディレクター: 全体の戦略設計、品質管理、スケジュール管理
- ライター/編集者: 企画、取材、執筆、校正
- デザイナー: アイキャッチ画像や図解の作成
- マーケター: SEO分析、効果測定、改善施策の立案
これらの役割を社内の人材でまかなうのか、あるいは専門知識を持つ外部パートナーに委託するのかを、自社のリソースやノウハウに応じて決定します。
ステップ5:ペルソナに響く「コンテンツ」を企画・制作する
体制が整ったら、いよいよコンテンツ制作の開始です。
ステップ2で設定したペルソナが、どのような課題を持ち、どんなキーワードで検索するかを想像しながら、コンテンツの企画を立てます。
単なる情報提供ではなく、「読者の課題を解決する」「読者にとって有益である」という視点を常に持ち、質の高いコンテンツを制作し続けることが成功の鍵です。
オウンドメディアの目的達成はプロに相談!テクロ株式会社が選ばれる理由
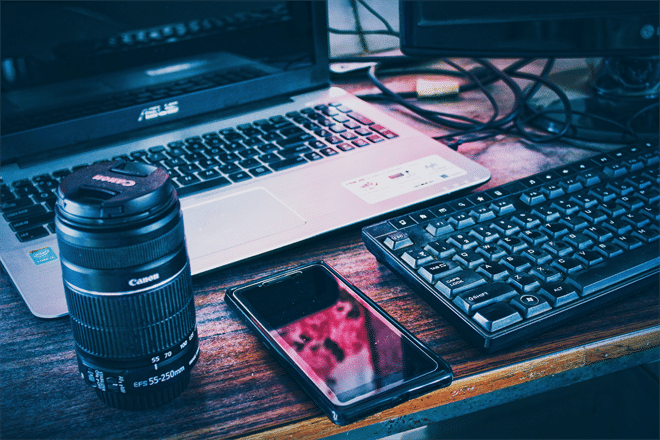
ここまでオウンドメディアの目的や始め方を解説してきましたが、「自社だけでは難しそうだ」「ノウハウやリソースが足りない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は、専門家の力を借りるのが最も確実な成功への近道です。
BtoB企業のオウンドメディア運用に課題をお持ちなら、ぜひ一度テクロ株式会社にご相談ください。
弊社が多くのクライアント様から選ばれ、成果を出し続けている理由を客観的なデータとともにお伝えします。
理由①:BtoB特化!データに基づく戦略でKPI達成率110%超えの実績
テクロは、BtoBマーケティングに特化したWebマーケティング会社です。
感覚的な運用ではなく、ウェブサイトデータやSEOデータ、顧客データなどを徹底的に分析し、データに基づいた戦略でクライアントのオウンドメディアを成功に導きます。
ご契約前にはシミュレーションを提示し、ご納得いただいた上でKPIを設定。
2024年度には、以下のような高いKPI達成率を記録しています。
- PV数達成率:112%
- CV数達成率:109%
- 開封率達成率:142%
- クリック率達成率:186%
BtoBマーケティング特有の課題や顧客行動を熟知しているからこそ、着実に成果に繋げることが可能です。
理由②:顧客満足度95%!各分野のプロフェッショナル集団による伴走支援
テクロの強みは、実績だけでなく、クライアントに寄り添う支援体制にもあります。
2024年度の顧客満足度調査では、総合満足度95%という高い評価をいただきました。
弊社のプロジェクトマネージャーは、BtoBマーケティング実務経験5年以上、Google Analytics認定資格などを保有するプロフェッショナル集団です。
オウンドメディアの立ち上げからSEOコンサルティング、MAツール導入支援まで、クライアントのビジネスステージや課題に合わせた最適なソリューションをワンストップで提供し、事業成長を力強く伴走支援します。
まずはお気軽に無料相談・資料請求から
オウンドメディアの目的設定や具体的な進め方、コンテンツ戦略について、少しでもお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
貴社の課題をヒアリングさせていただき、最適な解決策をご提案いたします。
詳しいサービス内容がわかる資料の請求も可能です。
まとめ|明確な目的設定でオウンドメディアを事業成長のエンジンに
本記事では、オウンドメディアの目的からメリット・デメリット、具体的な始め方までを解説しました。
- オウンドメディアの定義: 企業が自社で所有・運営するメディアで、情報発信の中核を担う。
- 4つの主要目的: 「集客」「ブランディング」「売上向上」「採用」であり、これらを明確にすることが成功の第一歩。
- メリット: 資産型の集客、コンテンツの二次利用、正確なブランディング、データ蓄積、採用ミスマッチ防止。
- デメリット: 成果が出るまでに時間がかかり、継続的なコストと専門ノウハウが必要。
- 始め方: 「目的・KGI設定」→「ペルソナ設計」→「KPI設定」→「体制構築」→「コンテンツ制作」の5ステップで進める。
オウンドメディアは、単に記事を公開するだけの場ではありません。
明確な目的のもとで戦略的に運用すれば、広告に頼らずとも顧客を集め、ブランドを育て、売上や採用に貢献する、まさに事業成長の強力なエンジンとなります。
この記事が、あなたの会社のオウンメディア成功への一助となれば幸いです。
なお、テクロ株式会社では「オウンドメディア作成マニュアル」資料を無料で配布しています。
マーケティング会社が実践しているオウンドメディアの作り方を知りたいBtoB企業様は、ぜひご確認ください。
「オウンドメディア作成マニュアル」をチェック!

- オウンドメディアの基礎知識
- 担当者が抱えるオウンドメディアの課題
- オウンドメディアを作る手順
- オウンドメディアを作るにあたって大切なこと
オウンドメディアの基本から立ち上げまでの手順を解説しています。「オウンドメディア作成マニュアル」をお気軽にダウンロードください。
オウンドメディアの導入によるメリットとデメリットは何ですか?それぞれについて詳しく教えてください。
メリットには広告費に依存しない資産型の集客が可能、コンテンツの二次利用による効率化、自社の情報コントロールとブランディングの精度向上、顧客データ蓄積と分析による事業改善、採用ミスマッチの防止とコスト削減があります。一方、デメリットには効果が出るまで時間がかかること、継続的なコンテンツ制作のコストやリソース、運用ノウハウの不足が挙げられます。
オウンドメディアを始める際に目的設定が重要な理由は何ですか?また、その方法についても教えてください。
目的設定は、オウンドメディア成功の鍵であり、曖昧なまま始めると方向性を見失い、効果も出ません。具体的には、目標をSMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き)に設定し、自社の事業課題に直結した明確なKGIを決めることが重要です。
オウンドメディアの主な目的は何ですか?それぞれの目的について教えてください。
オウンドメディアの主な目的は四つあり、潜在層にアプローチし集客すること、企業の想いや理念を伝えてブランディングを強化すること、顧客育成を通じて売上向上に貢献すること、そして自社の魅力を発信して採用活動を促進することです。これらによって、企業は多角的に事業拡大を目指します。
オウンドメディアとは何ですか?その基本的な役割は何ですか?
オウンドメディアとは、企業が自社で所有し管理・運営するメディアの総称であり、Webサイトやブログ、広報誌などが含まれます。その役割は、見込み顧客の獲得、ブランディング、顧客育成、採用促進など、戦略的に情報を発信し、事業の成長を支援することです。