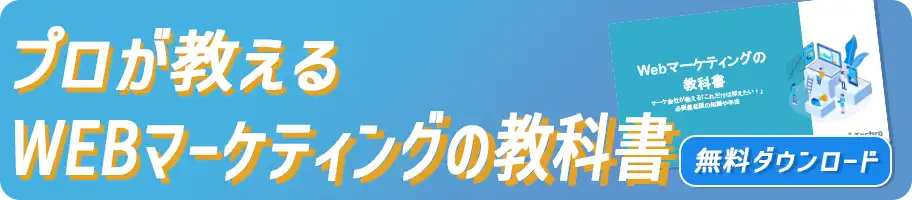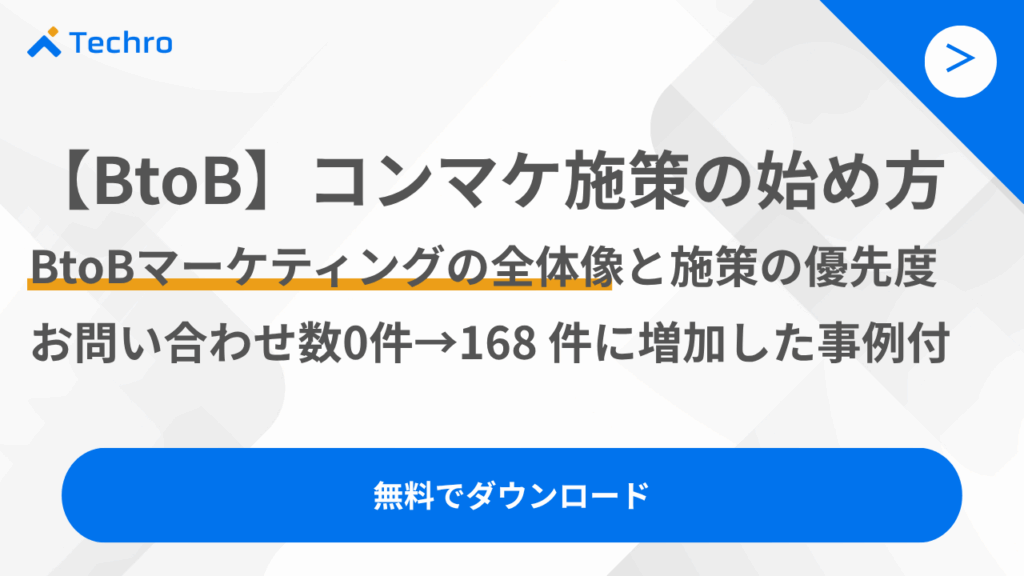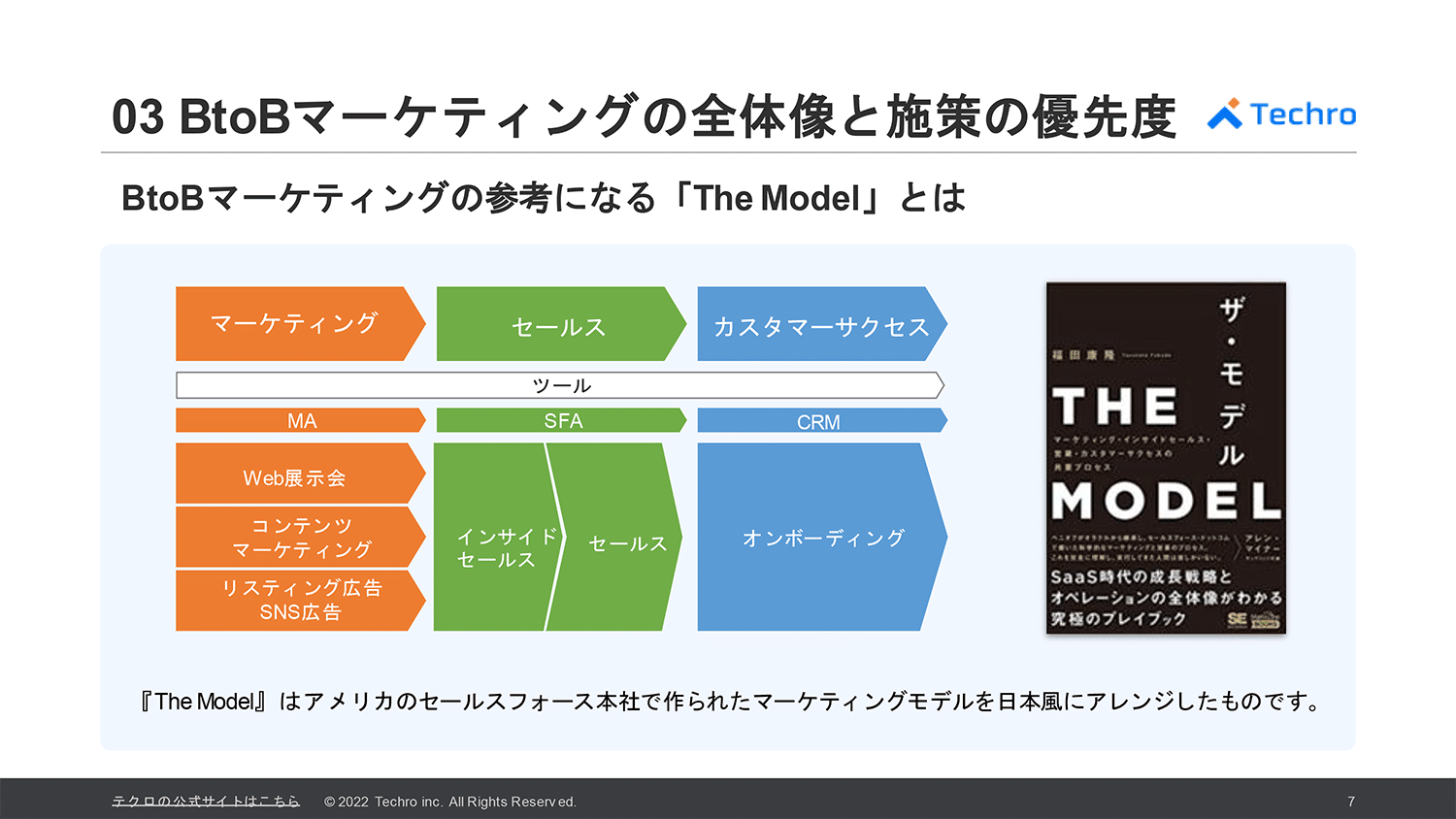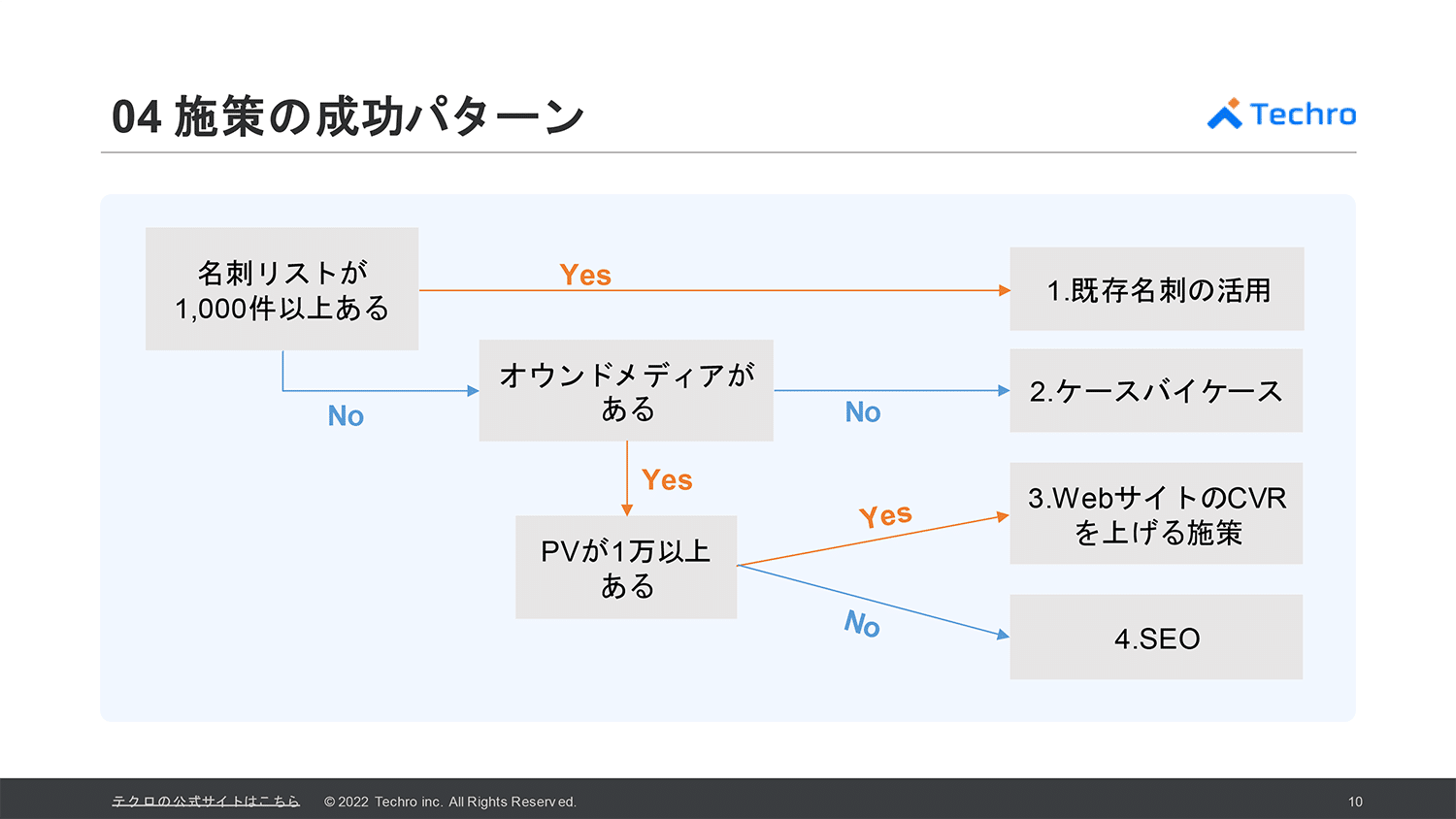コンテンツマーケティングとは?仕組み・メリット・実践方法まで徹底解説【2026年版】

「広告の効果が落ちてきた」「展示会だけでは限界がある」
そう感じている企業の多くが今、“売り込まずに選ばれる”仕組みとして注目しているのが、コンテンツマーケティングです。
かつての営業は、電話や飛び込み、広告で顧客にリーチする“アウトバウンド”型が主流でした。しかし、いまや顧客は自ら情報を調べ、比較し、納得した上で購入を決める時代。
「自社を見つけてもらい、信頼を獲得し、選ばれる」仕組みづくりが企業成長のカギとなっています。
この記事では、
- コンテンツマーケティングの基本・実践方法
- 導入時の注意点
- 導入成功事例
までを、実務担当者・決裁者の両視点でわかりやすく解説します。
BtoB向けのコンテンツマーケティングの全体像の解説や成功事例を紹介した「【BtoBのリード獲得に繋がる】コンテンツマーケティング施策の始め方」も無料配布していますので併せて参考にしてみてください。
目次
コンテンツマーケティングとは
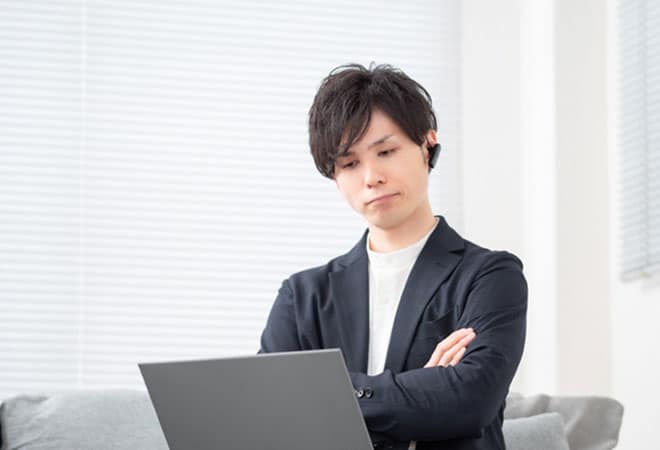
コンテンツマーケティングとは、「顧客にとって有益な情報(=コンテンツ)を継続的に提供し、信頼関係を築いた上で最終的に行動を促すマーケティング手法」です。
コンテンツには、以下のようなものが含まれます。
- テキストコンテンツ
- 画像コンテンツ
- 漫画コンテンツ
- 動画コンテンツ
自社の商品・サービスをいきなり売り込むのではなく、相手に“見つけてもらい”、“必要だと思ってもらい”、“選ばれる”ように設計するプロセスが特徴です。
従来の広告や営業とは異なり、コンテンツマーケティングではユーザーの検索行動やSNSでの情報収集を起点に、 「役立つな」「信頼できそうだな」と感じてもらうことで、商談や問い合わせにつながる状態を作ります。
なぜ今、コンテンツマーケティングが注目されているのか?
1. 顧客行動の変化
情報収集の起点が営業や広告から「検索」「SNS」「口コミ」に変わった今、一方的なアプローチでは興味を持ってもらえません。
ユーザーは、自分の課題を解決してくれそうな企業を“自ら探す”ようになっています。
2. 広告への依存リスク
広告費の高騰や、クリック率・CV率の低下など、短期施策だけでは安定した集客が難しくなっている企業も増えています。
広告と違って、コンテンツは“蓄積型”の施策。やればやるほど資産になるのが最大の特長です。
3. 中長期的な営業効率の改善
優良なリードを営業が追いかけ続けるには限界があります。
一方で、コンテンツによって“見込み度の高い顧客”が育ってくれば、営業の打ち手も効率的になります。
広告・営業との関係性
コンテンツマーケティングは、広告や営業と“対立する手法”ではありません。 むしろ、それらの成果を最大化するための“土台”となる存在です。
このように、マーケティングファネル全体の“質”を高めるハブとして機能するのがコンテンツマーケティングです。
- コンテンツで興味を喚起 → 広告でリターゲティング
- コンテンツでリードを獲得 → 営業が受注までつなげる
マーケティングファネルについては、こちらの記事もあわせてご参照ください。
→コンテンツマーケティングにおけるファネルとは?メリットやフェーズを解説
コンテンツマーケティングの主な種類と特徴
コンテンツマーケティングと一口に言っても、その手法は多岐に渡ります。ここでは、特にBtoB企業で活用されやすい代表的な5つの種類を紹介します。
1. ブログ記事(オウンドメディア)
検索エンジン経由の集客を狙う際に有効な手法です。見込み顧客が課題を検索したタイミングで、自社記事が上位表示されれば、自然な形で接点を作ることができます。
| 目的 | ポイント |
|
|
関連記事 : コンテンツマーケティングとオウンドメディアの違いを徹底解説
2. ホワイトペーパー・eBook
課題解決に役立つ資料やノウハウ集をPDFなどで提供し、ダウンロードと引き換えにリード情報を獲得する施策です。マーケティングの“入り口”として多く活用されています。
| 目的 | ポイント |
|
|
3. メルマガ/マーケティングオートメーション(MA)
獲得したリードと継続的に接点を保ち、購買意欲を育てていくための手法です。MAツールを使えば、行動ログに応じたステップメールなどの自動化も可能になります。
| 目的 | ポイント |
|
|
4. ウェビナー・動画コンテンツ
情報量の多いサービスやBtoB領域で、信頼醸成・検討促進に効果的なコンテンツの1つです。ウェビナー後のアンケートや資料DLなど、アクションも取りやすいのが特徴です。
| 目的 | ポイント |
|
|
5. SNSコンテンツ(主にBtoBならX/LinkedInなど)
ブランディングや人材採用にも効く、認知拡大型のコンテンツチャネル。親しみやすさやリアルな“人の声”を届ける場として活用されています。
| 目的 | ポイント |
|
|
関連記事 : コンテンツマーケティングの作り方を5つのステップと注意点を解説
導入する目的と得られるメリット
目的整理|短期と中長期で考えるべきこと
コンテンツマーケティングの目的は、「なんとなく集客のため」ではありません。企業の売上・営業効率に直結する“戦略的施策”として、明確な目的を持って導入することが重要です。
目的は、大きく次の2軸で捉えると効果的です。
| 短期的な目的(1年以内) | 中長期的な目的(1〜3年) |
|
|
コンテンツマーケティングの主なメリット
1. 広告に頼らない“自走型集客”が実現する
広告は即効性がある反面、止めればゼロになります。
コンテンツは、長く検索流入や信頼構築に寄与する「資産」として積み上がります。
関連記事 : コンテンツマーケティングの学習におすすめ本を分野別に20冊紹介
2. 営業工数を削減できる
「導入前にほぼ理解してくれていた」
「勝手に比較して、好印象だったから問い合わせた」
――このような“温度の高いリード”を生み出すことで、営業の負担やコールドコールの回数を減らせます。
3. ナーチャリングが自動化できる
資料DL→メール配信→ウェビナー視聴…といった購買検討フェーズに応じた設計が可能。
リードの温度感に応じて次のアクションに自然につなげられるため、営業のタイミングも最適化されます。
4. 社内のナレッジとしても機能する
コンテンツは、営業資料、FAQ、社内教育、マニュアル、採用PRなど、再活用性が非常に高いのも特長。
他部署との連携強化にもつながります。
実際の活用方法|どこから始めて、どう進めるか?
コンテンツマーケティングは、闇雲に記事を書き始めても成果にはつながりません。
重要なのは、「誰に、どんな価値を、どう届けるか」を明確にし、戦略→設計→実行→改善のサイクルを一貫して行うことです。
以下では、導入から運用までの基本的なステップを5段階に分けて解説します。
STEP1|ターゲットと提供価値の明確化
最初にやるべきは、「誰の、どんな課題を解決するのか?」を明確にすることです
ここがあいまいなまま進めると、読者に届かないコンテンツになってしまいます。
- メインターゲットは誰か(業種、職種、役職、フェーズ)
- どんな情報を欲しがっているのか
- 自社ならではの提供価値は何か
この段階では、既存顧客のインタビューや営業とのすり合わせが非常に有効です。
STEP2|カスタマージャーニーとコンテンツ設計
次に行うのが、ユーザーの検討プロセスに合わせたコンテンツの設計です。
認知→興味・関心→比較・検討→決定の各フェーズごとに、「どんな悩みがあるか」「どんな情報を届けるべきか」を整理します。
設計の具体例
- メインターゲットは誰か(業種、職種、役職、フェーズ)
- どんな情報を欲しがっているのか
- 自社ならではの提供価値は何か
STEP3|KPI・KGIの定義と測定設計
施策を継続的に改善するには、数値による効果測定の仕組みが欠かせません。
定量的な指標(例)
- 月間オーガニック流入数
- コンバージョン数(CVR)
- 資料DL数、CTAクリック率
- 商談化率、受注単価
ツールとしては、Google Analytics 4、Search Console、ヒートマップ、CRM/MAツールなどが活用されます。
STEP4|制作体制の構築と運用計画
次に、実際のコンテンツを「誰が、どのくらいの頻度で、どのように作るのか」を設計します。
主な検討ポイント
- 社内で書くか、外部に依頼するか
- 月間の本数、テーマの選定ルール
- 校正・チェック体制
- 発信スケジュールと運用ルール(CMS・SNS・MA配信など)
自社リソースが限られる場合は、「戦略・設計だけ社内で行い、制作は外注」という形も有効です。
STEP5|改善とナーチャリング施策への展開
主な検討コンテンツは公開して終わりではなく、成果を見ながら改善し続けることが重要です。
- 成果が出ているコンテンツのリライト・強化
- 反応の薄い記事の改善・削除・再活用
- ダウンロードしたリードへのフォロー施策(ステップメール、営業アプローチ)
マーケティング活動全体を“点”ではなく“線”でつなげていくことで、より高い成果を生み出すことができます。
よくある課題と導入前に知っておくべき注意点
コンテンツマーケティングは正しく設計・運用すれば高い効果を発揮しますが、導入初期にありがちな落とし穴も存在します。
ここでは、実際によくある3つの課題と、それを防ぐための注意点を紹介します。
1. 「記事は書いたが成果が見えない」
よくあるケースは、ブログや記事を定期的に更新しているものの、流入もCVもほとんどないという状態です。
| 原因の例 | 対策 |
|
|
2. 「続かない・属人化して終わる」
コンテンツ施策が“担当者個人の熱意頼み”になっていると、体制変更や多忙を理由に止まってしまいがちです。
| 原因の例 | 対策 |
|
|
3. 「営業との連携が取れておらず、活用されない」
良質なコンテンツを制作しても、営業に共有されず、リード活用されないまま終わるケースも少なくありません。
| 原因の例 | 対策 |
・マーケティングと営業の連携が希薄 ・リード情報の質や活用方法が共有されていない ・コンテンツを営業が“使える状態”になっていない | ・コンテンツの意図 / 使い方を営業チームとすり合わせる ・MAやSFAでリード情報を可視化・スコアリング ・営業用の資料化(トークスクリプト、比較表など)を行う |
成果を出すために必要なのは「仕組み」と「共通認識」です。コンテンツマーケティングは、単に記事を作るだけの施策ではありません。
「設計→実行→活用→改善」までを仕組み化し、社内外と連携して運用できる体制が成果につながります。
コンテンツマーケティングの成功事例

コンテンツマーケティングに取り組む際、ぜひ参考にしたいのが成功事例です。
2015年ごろから日本でも流行り始めたコンテンツマーケティングは多くの企業が取り入れていますが、その中には大きな成功を収めている企業もあります。
HAPPY PLUS STOREはECサイトをオウンドメディア化している事例で、バイヤーのレビューやコーディーネート術を配信しています。
OMG PRESSはメガネに特化したメディアで、顧客の悩みに寄り添ったコンテンツの発信によって大きな成果をあげている事例です。
SUUMOタウンは地域の情報を発信しているメディアで、街に住んでいるライターが記事を書いているため、リアルな雰囲気が伝わるなどの理由で人気を集めています。
実績を残しているメディアにアクセスして分析するだけでもヒントが得られるはずです。
その他の事例が知りたい方やそれぞれの事例についてさらに詳しく知りたい方は「コンテンツマーケティング成功事例25選!成果が出ている企業の共通点」もチェックしてみてください。
コンテンツマーケティングの勉強方法
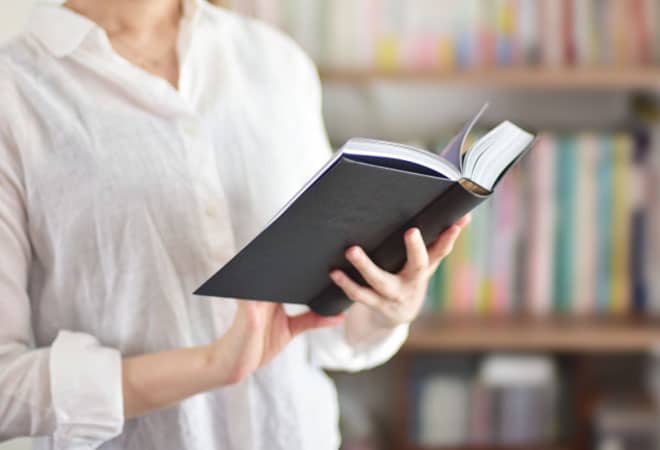
これからコンテンツマーケティングに取り組むのであれば、より深く学ぶことをおすすめします。なぜなら、学ぶほど知識が増え成功する確率が高まりますし、より良い成果をあげられるようになるからです。
また、すでに取り組まれている場合も、学ぶことで分析や改善の精度をより高められます。コンテンツマーケティングを学ぶのにおすすめの5つの勉強法について解説していきます。
勉強方法1. 本
コンテンツマーケティングは人気のマーケティング手法ですので、関連書籍が数多く発売されています。
Amazonで「コンテンツマーケティング」と検索すると400件以上の書籍が表示されることからも、人気ぶりがうかがえます。
数ある関連書籍の中でも、
などの書籍が有名です。
本は中身が厳しく精査された上で発売されるため正しい知識を身につけられますし、やるべきことが具体的に書かれていて体系的に学べます。
また「できるところからスタートする コンテンツマーケティングの手法88」のように、特定のテーマだけを深堀りして学べるのも本で学ぶメリットの一つです。
コンテンツマーケティングを学ぶのにおすすめの本について知りたい方は「コンテンツマーケティングは本で学ぼう!おすすめの良書を分野別に15冊紹介」を参考にしてみてください。
勉強方法2. Webサイトやブログ
本で学ぶ方法は、メリットがある反面
- 費用がかかる
- 最新の情報が入手しにくい
などのデメリットもあります。
本で学ぶ方法のそういったデメリットをカバーできる勉強方法が、Webサイトやブログで学ぶ方法です。
人気が高まっていることもあって、Webマーケティングのサービスを提供している企業のメディアを中心に、コンテンツマーケティングをテーマにしたWebサイトやブログが数多く登場しています。海外の最新の情報を翻訳する形で公開しているWebサイトやブログもあるほどです。
有名なWebサイトや著名な方のブログをいくつかブックマークしておいて、毎日のチェックを習慣化しておけば、コンテンツマーケティングについてかなり詳しくなれるでしょう。
ただ、不確かで根拠のない情報や古い情報も発信されているため、参考にするWebサイトやブログの取捨選択が重要です。
勉強方法3. SNS
SNSもコンテンツマーケティングが学べる便利なツールの一つです。
特におすすめのツールがFacebookとX(Twitter)です。
専門家のリアルな意見を聞きたいなら「X(Twitter)」がおすすめ
専門家のリアルな意見を聞きたいのであれば、おすすめは「X(Twitter)」です。
コンテンツマーケティングに欠かせない、
- SEO
- ライティング
- 分析
- SNS
など、それぞれの分野の専門家がおり、日々参考になる情報をつぶやいているため、フォローしてタイムラインを眺めているだけでも勉強になるはずです。
過去のツイートをさかのぼって勉強するのもいいでしょう。
中には大企業で、コンテンツマーケティングを担当しているユーザーや海外の最新の情報を積極的に発信しているユーザーもいます。
まれに書籍やWebサイトではお目にかかれない有料級の情報が出されることもあるため、それぞれの分野で有名な方をフォローし、学習の参考することをおすすめします。
コミュニティを通して知識を得たいなら「Facebook」がおすすめ
コンテンツマーケティングの勉強には「Facebook」も活用できます。
Facebookではグループの機能があり、コンテンツマーケティングをテーマにしたコミュニティに入れば、公開されている投稿で学べます。グループに参加することで、同じくコンテンツマーケティングを学びたいと考えているユーザーと一緒に知識を深めたり、詳しいユーザーに教えてもらったりできるでしょう。
楽しみながらコンテンツマーケティングへの理解を深めたい方におすすめです。
勉強方法4. 動画配信プラットフォーム
コンテンツマーケティングの学習方法の中でも最先端をいっているのが、動画配信プラットフォームを活用する学び方です。
主に無料で視聴可能な「YouTube」がおすすめです。
これまで紹介してきた学習方法に比べると、教材や情報の充実度では見劣りしてしまいます。しかし、最近はYouTubeにもビジネス系の情報を発信するチャンネルが増えてきており、コンテンツマーケティングに関する動画も多数アップされている特徴があります。
動画は本やWebサイトなどに比べると得られる情報量は多く、
- 映像
- 画像
- 音声
で構成されており、本やサイトよりも情報量が多いため、難しい内容を学ぶのにおすすめです。
ただ、それほど実績のない方が間違った情報を発信しているケースも少なくないため、どの動画で学ぶかを慎重に選ばなくてはいけません。
勉強方法5. オンラインスクール
動画で学べるオンラインスクールもおすすめです。
YouTubeは学習を目的としたプラットフォームではないため、本のように体系的に学べません。その反面オンラインスクールは、学習を目的としているため、YouTubeの動画よりもわかりやすく、本のように体系的に学べます。
代表的なサービスには、世界中で利用されている「udemy」が挙げられます。udemyはイラストなどの趣味に関することからマーケティングなどのビジネスに関することまで、さまざまなスキルを動画で学べるオンラインスクール型のサービスです。
視聴するにはコンテンツを購入しなくてはいけませんが、書籍と変わらない値段で購入できるものも多いため、ぜひ一度サイトをのぞいてみてはいかがでしょうか?
勉強方法6.セミナー
「第一線で活躍している方から学びたい!」と考えている方におすすめなのが、セミナーです。
コンテンツマーケティングは注目されているマーケティング手法であるため、関連するセミナーがたびたび開催されています。
有料のセミナーも少なくありませんが、セミナーには、
- 一流の講師から学べる
- 外部に出ていない知見や情報が得られる
- 質問できる
など、他の勉強方法にはない魅力的なメリットがいくつもあります。
また、セミナーの講師や他の参加者と交流できることもメリットの一つです。同じくコンテンツマーケティングに取り組んでいる方との交流を深めておけば、ノウハウや情報を共有できるため、学習に大いに役立ちます。
ただ、他の学習方法と同じくそれほど目立った実績のない講師が高額でセミナーを開催していたり、参加者に高額な商材を売りつけていたりすることもあります。セミナーならではのトラブルもあるため注意が必要です。
コンテンツマーケティングに関するよくある質問
最後に、コンテンツマーケティングに関するよくある質問をQ&Aの形式で紹介していきます。
Q1. 内製と外注のどちらで取り組むべきでしょうか?
A. 内製と外注のどちらで取り組むべきかについては、スケジュール感や予算感によって異なります。
予算が確保できない場合や、スケジュールが差し迫っていない場合はコスト対策・知見や経験を得るために、内製で取り組んでもいいでしょう。しかし、スピード感を持って取り組みたい場合や成果をあげたい場合は、外注がおすすめです。
コンテンツマーケティングは、専門家にお願いした方が成功する確率を高められます。社内にコンテンツマーケティングやコンテンツの制作に明るい社員がいない場合、制作方法や施策をイチから学んでいかなくてはいけません。
するとどうしても時間がかかりますし、質の高いコンテンツを作るのも難しくなってしまうでしょう。プロにサポートしてもらうことで、記事の改善点や効果的な施策を教えてもらえます。
予算に余裕があり、コンテンツの制作方法をしっかり学びたい場合は、外注することも検討してみてください。
外注化に関してさらに知りたい方は「コンテンツマーケティングに強い会社10選!選び方のポイントも解説」をご覧ください。
Q2. すべてのプラットフォームを活用するべきでしょうか?
A. コンテンツマーケティングにおいて制作したコンテンツを発信できるプラットフォームや発信の方法には、
- Webサイト
- ブログ
- SNS
- 動画配信プラットフォーム
- メール
- 広告
など、さまざまな種類があると紹介してきました。
それぞれ特徴が異なるため、初めてコンテンツマーケティングに取り組む方は、すべてのプラットフォームを活用するべきだと考えてしまいがちです。ただし、初心者で内製して進めていくのであれば、いきなりすべてのプラットフォームを活用しようと考えるのは得策ではありません。
経験やノウハウがない状態でいきなりすべてのプラットフォームに手を出してしまうと、すべてが中途半端になり、計画が頓挫してしまう可能性が高まります。そのため、内製で進める場合は、注力するプラットフォームを絞った上で取り組み始めてください。
ペルソナを設定した後に、利用するであろうツールを選択することがおすすめです。
Webマーケティング会社などに外注する場合はそちらの提案に従って進める方が効率が良いですし、成果も出やすくなるでしょう。
Q3. 毎日更新していたらアクセスが集まるようになりますか?
A. ユーザーとの接点を増やすため、コンテンツは毎日制作して更新するべきと考える方は少なくありません。実際、ブログの場合はそういった主張がいまでも目立ちます。
確かにコンテンツの数多ければ多いほどリーチできるユーザーも多くなりはしますが、どのプラットフォームでもユーザーに届くのは「質の高いコンテンツ」です。毎日更新を目標してしまうとどうしてもコンテンツの質が低くなってしまい、プラットフォーム側から評価されません。
そのため、これからコンテンツマーケティングに取り組むのであれば、とにかく質にこだわるようにしましょう。
質の高いコンテンツは決して簡単にできるものではないため、制作するのに数日、あるいは数週間かかってしまう場合もあります。しかし、質の高いコンテンツがアクセスやファンの獲得につながるため、ユーザーを満足させれられるよう心がけてください。
Q4. 有料のツールは活用するべきでしょうか?
無料版だと最低限の機能しか利用できないため、必要に応じて有料のツールも導入を検討してみましょう。
確かにいずれのツールも高機能なものばかりですが、コンテンツマーケティングに取り組み始めたばかりの段階導入するのは困難です。
これらのツールを導入した場合、操作方法や活用方法を学ぶ必要がありますが、時間をかけるくらいであれば一つでもコンテンツを多く制作するべきです。有料ツールは、結果が出始めた段階で、より成果を高めるために導入するかどうか改めて検討するといいでしょう。
まとめ|コンテンツは「資産」になる。だからこそ戦略的に
コンテンツマーケティングは、単なる情報発信ではありません。 「顧客の意思決定プロセスに寄り添い、選ばれる状態をつくる仕組み」です。広告のように即効性はありませんが、正しく設計すれば、 中長期的に集客・育成・営業支援の土台となる“資産”になります。
そして、成果につながるコンテンツをつくるためには、 「誰に、何を、どう届けるか」を明確にした上で、 設計・制作・運用・改善を一貫して行う体制づくりが不可欠です。
「続かない」「社内に知見がない」「忙しくて手が回らない」 そんな悩みがある場合は、信頼できる外部パートナーとの連携を視野に入れてみてください。
テクロでは、BtoB領域のスタートアップ・中小企業を中心に 戦略設計から記事制作、運用改善まで一貫して支援しています。
- オウンドメディアの立ち上げに不安がある
- SEOを軸にした集客基盤をつくりたい
- 記事制作だけでなく、戦略部分から相談したい
- 営業やMAと連動した成果設計まで行いたい
といった課題をお持ちでしたら、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。
コンテンツマーケティングの成功事例にはどのようなものがありますか?
HAPPY PLUS STOREやOMG PRESS、SUUMOタウンなどの事例があります。これらはオウンドメディア化や専門性の高い情報発信により、大きな成果を挙げている例です。
コンテンツマーケティングの導入際に注意すべき課題は何ですか?
記事だけを書いても成果が見えない、続かない属人化、営業と連携が取れないなどが挙げられます。これらを防ぐためには適切な設計と仕組み化、社内外の連携が必要です。
コンテンツマーケティングに適した種類と特徴は何ですか?
代表的な種類にはブログ記事、ホワイトペーパー・eBook、メルマガ・MA、ウェビナー・動画、SNSコンテンツがあります。それぞれ検索エンジンからの集客やリード獲得、信頼醸成、認知拡大などに効果的です。
なぜ今、コンテンツマーケティングが注目されているのですか?
顧客の情報収集の方法が変化し、アウトバウンド型の営業や広告だけでは効果が限定的になっているためです。また、広告依存のリスクや中長期的な営業効率の改善にも寄与するため、今注目されています。
コンテンツマーケティングとは何ですか?
コンテンツマーケティングは、顧客にとって有益な情報(コンテンツ)を継続的に提供し、信頼関係を築きつつ最終的に行動を促すマーケティング手法です。