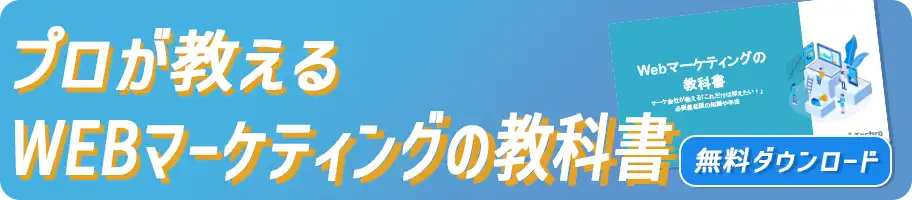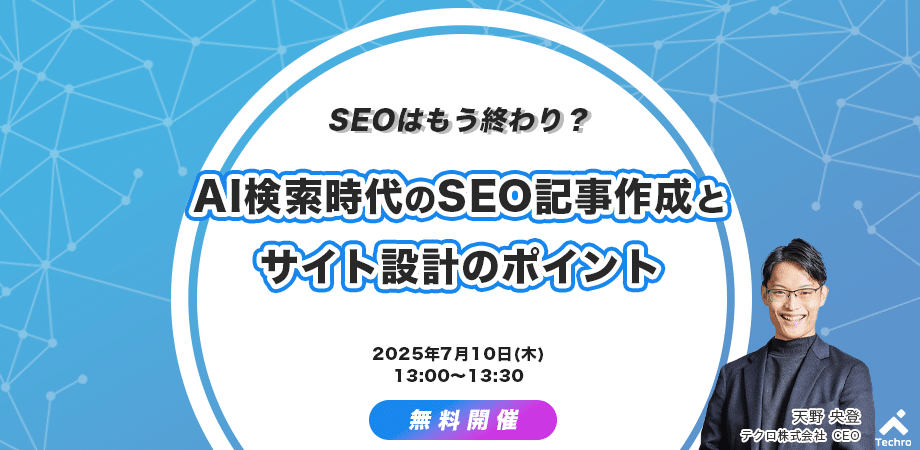記事作成代行とは?依頼方法・メリット・費用相場まで徹底解説【2025年版】

「自社サイトのアクセス数が伸び悩んでいる…」
「コンテンツマーケティングの重要性は分かっているが、記事を書く時間も人材も足りない」
「外注したいけど、料金相場や良い会社の選び方が分からなくて不安」
オウンドメディアやWebサイトを運営する中小企業の担当者様、経営者様の中には、このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなお悩みを解決する「記事作成代行サービス」について、専門知識がない方でも分かるように徹底解説します。
料金相場やサービスの種類といった基本的な情報から、自社に最適なパートナーを見つけるための具体的な選び方、おすすめの代行会社まで網羅しました。
この記事を最後まで読めば、記事作成代行に関する不安が解消され、Webサイトからの集客増や売上向上という目標達成に向けた、確かな一歩を踏み出せるはずです。
手間のかかる記事作成業務を専門家に任せ、あなたは本来注力すべきコア業務に集中しましょう。
なお、テクロ株式会社では「オウンドメディア運用代行サービス」資料を無料で配布しています。
法人リード獲得に課題を持つ BtoB企業様はぜひご確認ください。
導入事例から見るオウンドメディア運用代行サービス!
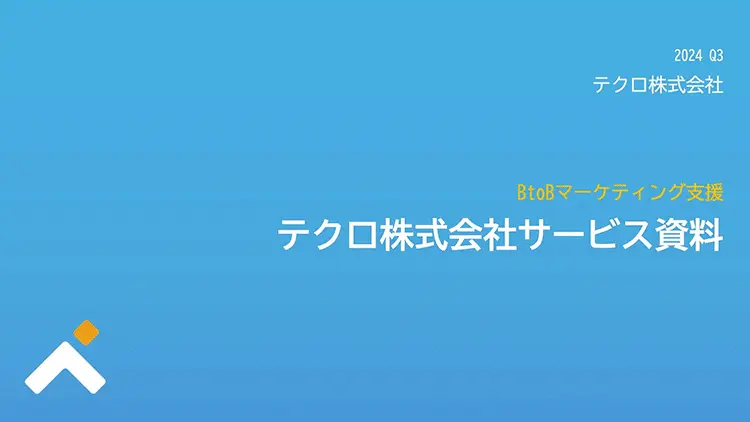
- 新たな集客手段を作りたい
- 問い合わせを増やしたい
- 運用を専門家に任せたい
オウンドメディアの立ち上げから実務まで代行した導入事例を紹介しています。「オウンドメディア支援サービス資料」をお気軽にダウンロードください。
目次
- 1 そもそも記事作成代行とは?急成長する市場の背景
- 2 記事作成代行を利用するメリット・デメリット
- 3 【料金表あり】記事作成代行の費用相場を徹底解説
- 4 どこに依頼する?記事作成代行サービスの4つの依頼先
- 5 【最重要】失敗しない記事作成代行会社の選び方8つのチェックリスト
- 6 【目的別】おすすめの記事作成代行会社・サービス15選を比較
- 7 依頼から納品までの基本的な流れ5ステップ
- 8 【実例】記事作成代行のよくある失敗事例3選とその対策
- 9 記事作成代行の成功事例と今後の展望
- 10 まとめ:自社に最適な記事作成代行パートナーを見つけ、事業を加速させよう
- 11 また、テクロが目指すのは、単発のコンテンツ制作ではありません。中長期的なマーケティング成果(リード獲得、商談化率アップ、ブランド形成)を見据え、戦略設計から伴走しながら、クライアントとともに成長するパートナーであり続けます。
そもそも記事作成代行とは?急成長する市場の背景
記事作成代行とは、企業や個人に代わって、専門のライターや編集者がWebサイトやブログに掲載する記事を作成するサービスのことです。
SEO対策を施した記事や、専門性の高いコラム、ユーザーの購買意欲を高めるレビュー記事など、クライアントの目的に合わせたコンテンツを提供します。
近年、Webサイトを通じて見込み客を獲得するコンテンツマーケティングの重要性が高まっています。
実際に、2024年のコンテンツマーケティング市場規模は約3,000億円と推定され、今後も拡大が見込まれています。
このような背景から、専門知識やリソースが不足しがちな中小企業を中心に、記事作成代行サービスの需要が急速に高まっているのです。
記事作成代行を利用するメリット・デメリット
記事作成代行サービスを導入すべきか判断するためには、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが不可欠です。
ここでは、定量的なデータや具体的な事例を交えながら、双方の側面を客観的に見ていきましょう。
自社の状況に置き換えて、導入後の姿をイメージしてみてください。
【効果絶大】記事作成代行の4つの主要メリット
記事作成代行サービスを活用することで、企業は多くのメリットを享受できます。
コア業務に集中できる時間と労力の創出
- 記事の企画、執筆、校正には膨大な時間がかかります。
- これらを外部の専門家に任せることで、担当者は本来注力すべき商品開発や営業活動などに集中できます。
SEOに強い高品質な記事による集客力向上
- 専門のライターや編集者が、SEO対策を施した質の高い記事を作成します。
- ある調査では、記事作成代行サービスを利用した企業のWebサイトトラフィックは平均で40%増加し、SEOランキングは平均25%向上したというデータもあります。
継続的なコンテンツ発信による資産構築
- 定期的な記事更新は、サイトの評価を高め、ファンを育成する上で非常に重要です。
- 代行サービスを使えば、安定的かつ継続的にコンテンツを発信し、企業の信頼性や専門性を高めることができます。
採用・教育コストをかけずに専門チームを確保
- 自社で専門ライターを雇用・育成するには、多大なコストと時間がかかります。
- 代行サービスなら、必要な時に必要な分だけ、質の高いライティングチームのリソースを活用できます。
実際に、株式会社インタースペースは記事作成代行サービスの利用により、わずか6ヶ月でWebサイトへのアクセス数が150%増加し、売上30%向上という大きな成果を上げています。
知っておくべき4つのデメリットと潜在的リスク
多くのメリットがある一方で、デメリットやリスクも存在します。
これらを事前に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。
費用の発生
- 当然ながら、外部に依頼するため費用が発生します。
- 記事の品質や文字数、専門性によって料金は大きく変動するため、予算計画が重要になります。
コミュニケーションコスト
- 記事の目的やターゲット、ニュアンスなどを正確に伝えるためのコミュニケーションが必要です。
- この連携がうまくいかないと、期待通りの記事が上がってこない可能性があります。
品質のばらつき
- 依頼する会社やライターのスキルによって、記事の品質にばらつきが出ることがあります。
- 特に格安のサービスでは、品質管理が不十分なケースも見受けられます。
情報伝達の非効率性と潜在コスト
- 社内の情報や微妙なニュアンスを外部のライターに伝えるには手間がかかります。
- 認識の齟齬から期待と異なる記事が納品され、修正に多大な時間と費用がかかり、結果的に約70万円の損失につながったという失敗事例もあります。
【料金表あり】記事作成代行の費用相場を徹底解説
「実際にいくらかかるのか?」は、担当者様が最も気になるポイントでしょう。
記事作成代行の費用は、主に「料金体系」「記事の種類」「追加オプション」によって決まります。
ここでは、それぞれの詳細な相場観を解説し、予算策定の参考にしていただける情報を提供します。
料金体系は3種類!文字単価・記事単価・月額制の違い
記事作成代行の料金体系は、主に以下の3種類に分けられます。
自社の発注頻度や予算、管理の手間などを考慮して、最適なプランを選びましょう。
| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|---|---|
| 文字単価 | 1文字あたりの単価で費用を算出する最も一般的な形式。 | 費用感が分かりやすく、少ない本数からでも依頼しやすい。 | 文字数が多くなると費用が高額になる。 | まずはお試しで数本依頼したい企業 |
| 記事単価 | 1記事あたりの固定料金で契約する形式。 | 構成や企画込みの場合が多く、文字数を気にせず発注できる。 | 文字数が少ないと割高になる可能性がある。 | 記事の品質や企画から任せたい企業 |
| 月額制 | 毎月決まった本数や文字数の記事を制作する契約形式。 | 継続的に発注することで単価が割安になる。安定したコンテンツ更新が可能。 | 毎月固定の費用が発生する。 | オウンドメディアを本格的に運用したい企業 |
【一覧表】記事タイプ別の費用相場と料金内訳
記事の内容や専門性によって、料金は大きく変動します。
以下は、記事タイプごとの費用相場と、その料金に含まれる作業の内訳です。
| 記事の種類 | 文字単価の相場 | 記事単価の相場 | 主な費用の内訳 |
|---|---|---|---|
| SEO記事 | 3円~6円 | 10,000円~30,000円 | キーワード選定(15%), 構成案作成(25%), 執筆(40%), 編集・校正(10%), SEO対策(10%) |
| 専門記事 | 3円~10円 | 15,000円~40,000円 | 専門家監修(25%), リサーチ(35%), 執筆(30%), 編集・校正(10%) |
| レビュー記事 | 1円~3円 | 5,000円~20,000円 | 商品調査(25%), 執筆(55%), 編集・校正(10%), 画像選定(10%) |
| インタビュー記事 | – | 30,000円~50,000円 | 取材(35%), テープ起こし(20%), 記事作成(35%), 編集・校正(10%) |
専門性が高くなるほど、リサーチや監修にコストがかかるため、単価は上がる傾向にあります。[^3]
オプション料金に注意!追加で発生する可能性のある費用
基本料金の安さだけで選んでしまうと、後から追加費用がかさむことがあります。
契約前には、以下のオプション料金についてもしっかりと確認しておきましょう。
- キーワードリサーチ: 5,000円~/キーワード
- 画像選定・作成: 1,000円~/枚
- WordPressなどへの入稿作業: 3,000円~/記事
- 専門家による監修: 20,000円~/記事
- 修正回数の追加: 1回あたり記事単価の20%~50%
- 短納期対応: 特急料金として20%~50%割増
これらの費用は代行会社によって大きく異なるため、契約内容を隅々まで確認することが重要です。[^4]
どこに依頼する?記事作成代行サービスの4つの依頼先
記事作成を依頼できる先は、大きく分けて4種類あります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の目的や予算、かけられるリソースに応じて最適な依頼先を選びましょう。
①記事作成代行会社|高品質でサポートも充実
記事作成を専門に行う会社で、ディレクターや編集者、校正者が在籍しています。
ライターの品質管理や進行管理、企画提案まで一貫して任せられるのが最大の強みです。
高品質な記事を安定的に制作したい、SEO戦略から相談したいという企業に最適です。
その分、費用は他の依頼先に比べて高くなる傾向があります。
②クラウドソーシング|低コストで手軽に依頼可能
Web上で不特定多数の人に業務を依頼できるプラットフォームです。
最大のメリットはコストを抑えられる点で、1記事数千円から発注することも可能です。
しかし、ライターのスキルや経験は玉石混交であり、当たり外れが大きいのが実情です。
品質管理やディレクションを自社で行う必要があるため、担当者の手間がかかる点を覚悟しなければなりません。
③フリーランスライター|専門分野に強い人材が見つかることも
個人で活動しているライターに直接依頼する方法です。
特定の業界やテーマに精通した、専門性の高いライターを見つけやすいのがメリットです。
代行会社を介さないため、比較的安価で柔軟な対応が期待できる場合もあります。
ただし、優秀なライターを探し出す手間や、契約・請求といった事務作業を自社で行う必要があります。
④AIライティングツール|スピーディーかつ低コスト(ただし注意点あり)
近年、急速に進化しているのがAIを活用したライティングツールです。
圧倒的なスピードと低コストで文章を生成できるため、記事のたたき台作成やアイデア出しには非常に有効です。
しかし、AIが生成した文章は、情報が古かったり、誤りを含んでいたりする可能性があります。
また、独自性や体験談に基づいた深い内容を書くことは困難です。
そのため、AIを全面的に頼るのではなく、あくまで人間の編集・校正を前提とした「アシスタント」として活用するのが賢明です。
【最重要】失敗しない記事作成代行会社の選び方8つのチェックリスト
数ある代行会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけ出すことは、プロジェクトの成否を分ける最も重要なプロセスです。
以下の8つのチェックリストを活用し、多角的な視点から慎重に評価・選定しましょう。
1. 目的とKPI(目標)を明確にする
まず、「何のために記事を作成するのか」という目的を明確にしましょう。
目的が曖昧なままでは、代行会社も的確な提案ができません。
- 目的の例
SEOで上位表示したい、サイトからの問い合わせを増やしたい、企業のブランディングを強化したい - KPIの例
PV数、セッション数、コンバージョン率、検索順位、指名検索数
これらの目的とKPIを具体的に伝えることで、代行会社との間に共通認識が生まれ、成果につながる記事作成が可能になります。
2. 実績と得意分野(特に自社業界)を確認する
代行会社の実績は、その実力を測る最も分かりやすい指標です。
特に、自社と同じ業界や近しいテーマでの実績があるかどうかは必ず確認しましょう。
- 公式サイトの制作実績や導入事例を確認する。
- 具体的なポートフォリオ(過去に制作した記事)の提出を依頼する。
- 事例を見る際は、どのような課題に対し、どういった施策で、どんな成果(具体的な数字)が出たのかを詳しくチェックしましょう。
3. 料金体系と契約内容を隅々まで確認する
料金の安さだけで選ぶのは非常に危険です。
後からトラブルにならないよう、契約前に以下の項目を必ず確認してください。
- 料金に含まれる業務範囲
企画、構成案、執筆、校正、修正、画像選定、入稿など、どこまでが基本料金に含まれるか。 - 修正回数の上限と追加料金
無料での修正は何回まで可能か、それを超えた場合の料金はいくらか。 - 著作権の帰属
納品された記事の著作権はどちらに帰属するのか。二次利用は可能か。
4. SEO対策に関する知識と実績は十分か
Webサイトからの集客を目指すなら、代行会社のSEOに関する知見は必須条件です。
単に文章が書けるだけでなく、検索エンジンに評価されるコンテンツを制作できる会社を選びましょう。
- 最新のGoogleアルゴリズムを理解しているか。
- キーワード選定や競合分析から提案してくれるか。
- 内部リンクの最適化や構造化データなど、テクニカルなSEOにも対応できるか。
SEO対策について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご参照ください。
→オウンドメディアで失敗しないSEO対策とは?効果的な方法を解説
5. コミュニケーションとサポート体制は円滑か
記事作成は一度依頼して終わりではなく、継続的なやり取りが発生します。
円滑なコミュニケーションが取れるかどうかは、プロジェクトの成功に直結します。
- 専任の担当者がつくか。
- 連絡手段(メール、チャット、電話)やレスポンスの速さはどうか。
- 定期的な進捗報告やミーティングの機会はあるか。
- 課題解決に向けて二人三脚で進めてくれる「伴走型」の支援体制か。
6. ライターや編集者の質と管理体制
記事の品質は、執筆するライターとそれをチェックする編集者の質で決まります。
どのような体制で品質を担保しているのかを確認しましょう。
- ライターの採用基準やテスト内容はどのようなものか。
- 専門分野に精通したライターは在籍しているか。
- 編集者や校正者によるダブルチェック、トリプルチェックの体制はあるか。
- コピペチェックは行っているか。
7. サンプル記事の提出やトライアルは可能か
契約前に、実際の記事の品質を確認することはミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。
- サンプル記事の提出
過去の制作実績ではなく、自社が依頼したいテーマで新たに1記事作成してもらう。 - トライアル(試験的な発注)
まずは少額・少量(例:3記事)で発注し、品質や進行のスムーズさを確認する。期間としては最低2ヶ月程度設け、品質の安定性を見極めるのがおすすめです。[^8]
8. 記事作成以外の対応領域(企画・入稿・分析など)
自社のリソース状況によっては、記事作成以外の業務も任せられると非常に助かります。
代行会社がどこまでの領域をカバーしてくれるのかを確認しましょう。
- コンテンツ全体の戦略立案
- メディアの立ち上げ支援
- WordPressなどへの入稿・装飾作業
- 公開後の効果測定と改善提案(リライトなど)
これらの8つのポイントを総合的に評価し、信頼できるパートナーを選びましょう。
【目的別】おすすめの記事作成代行会社・サービス15選を比較
ここからは、これまでの選び方を踏まえ、具体的な記事作成代行会社を目的別に分類してご紹介します。
「高品質な記事でリード獲得したいBtoB企業」「とにかく実績豊富な大手がいい」など、自社のニーズに合ったサービスを見つけてください。
【BtoB特化・伴走型支援なら】テクロ株式会社
BtoB企業のWebマーケティング、特にオウンドメディア運用で成果を出したいなら、まず検討すべきがテクロ株式会社です。
クライアントに寄り添う「伴走型支援」を強みとし、Web戦略の立案から実行、改善までを一気通貫でサポートします。
その実力は、数々の成功事例が証明しています。
- 株式会社LGブレイクスルー様: 半年間でPV数180%、リード獲得数を月30件から80件へと大幅に増加。
- 株式会社サムシングファン様: 1年間でPV数を1.5万から132万へ、資料請求数を月0件から168件へと飛躍的に向上。
- 株式会社アジャイルウェア様: 主要キーワードでのサイト表示が21倍に増加し、サービス利用者数は月1件から118件に増加。
これらの目覚ましい成果は、2024年12月の福岡証券取引所Fukuoka PRO Marketへの上場(証券コード:306A)という形で、市場からも高い評価を受けています。
上場を機にサービスプランも拡充し、より多様なニーズに応えられる体制を構築。BtoBマーケティングで確かな成果を求める企業にとって、最も信頼できるパートナーの一つと言えるでしょう。
テクロ株式会社の強み:データ分析に基づくBtoB特化戦略と月間1,200本の制作体制
テクロ株式会社の最大の強みは、データに基づいた論理的な戦略立案能力と、それを実行する圧倒的な制作体制にあります。
データドリブンな戦略
- SimilarWebやSEMrushといった専門ツールを駆使して競合サイトを徹底分析。
- Google Analyticsなどで顧客サイトの現状を正確に把握し、科学的なアプローチで最適なコンテンツ戦略を立案します。
BtoB特化の専門性
- BtoB企業特有の購買プロセスや顧客心理を深く理解し、リード獲得から商談化、受注までを見据えたコンテンツを制作します。
圧倒的な制作・支援体制
- 月間1,200記事という業界トップクラスの制作能力を誇ります。
- SEO、広告運用、MAツール導入支援まで、Webマーケティングを包括的にサポートできる専門家チームが、顧客の課題解決に向けて伴走します。
【大手で実績豊富】株式会社PLAN-B
「カグヤ」などの自社メディア運営で培ったノウハウと、大手企業を含む豊富な実績が魅力の会社です。
SEOコンサルティングに定評があり、データ分析に基づいた戦略的な記事作成を得意としています。
大規模なオウンドメディアの運用や、SEOで確実な成果を求める企業におすすめです。
【メディア運営ノウハウ】株式会社LIG
ユニークな企画と面白いコンテンツで知られる「LIGブログ」を運営するWeb制作会社です。
記事作成だけでなく、Webサイト制作やデザイン、動画制作なども含めて依頼できるのが強み。
読者のファン化や、企業のブランディングを目的としたコンテンツ制作をしたい場合に適しています。
その他、比較対象となる企業を12社、特徴を簡潔にまとめて紹介
世の中には、ほかにも多様な強みを持つ記事作成代行会社が存在します。
ここでは、比較検討の参考となる12社を一覧でご紹介します。
| 会社名 | 特徴 | 料金目安(文字単価) |
|---|---|---|
| 株式会社CINC | SEO分析ツール「Keywordmap」を自社開発。データドリブンな記事制作が強み。 | 5円~ |
| 株式会社ウィルゲート | 9,400社以上の支援実績。SEO記事から専門性の高い記事まで幅広く対応。 | 4円~ |
| 株式会社YOSCA | ライター・編集者約1,500名が在籍。高品質な記事を大量に制作可能。 | 3円~ |
| 株式会社GIG | Webコンサルティングから制作、運用までワンストップで提供。 | 要問い合わせ |
| アズ株式会社 | 医療・美容・健康分野に特化。薬機法や医療広告ガイドラインに準拠。 | 5円~ |
| 株式会社Bridge | 金融・不動産分野に特化。FPや宅建士などの有資格者が執筆・監修。 | 6円~ |
| ランサーズ株式会社 | 日本最大級のクラウドソーシング。低コストで手軽に依頼可能。 | 1円~ |
| 株式会社クラウドワークス | ランサーズと並ぶ大手クラウドソーシング。多様なライターが登録。 | 1円~ |
| 株式会社CROCO | 構成案作成に特化したプランあり。ディレクション体制が強み。 | 3.5円~ |
| 株式会社EXIDEA | 海外SEOにも強い。多言語での記事作成に対応可能。 | 要問い合わせ |
| 合同会社記事作成代行屋 | 文字単価1円~という低価格が魅力。コストを最優先したい場合に。 | 1円~ |
| サグーワークス(株式会社ウィルゲート) | ライターテスト制度が充実。クラウドソーシングの中でも品質が安定。 | 1.5円~ |
依頼から納品までの基本的な流れ5ステップ
初めて記事作成代行を利用する方でも安心して進められるよう、依頼から納品までの一般的な流れを5つのステップで解説します。
問い合わせ・ヒアリング
- まずは公式サイトのフォームなどから問い合わせます。
- その後、代行会社の担当者と打ち合わせを行い、記事作成の目的、ターゲット、予算、希望する記事のテーマや本数などを伝えます。
提案・見積もり・契約
- ヒアリング内容に基づき、代行会社から具体的な施策の提案と見積もりが提示されます。
- 内容に納得したら、契約を締結します。この際、業務範囲や納期、支払い条件などを改めて確認しましょう。
構成案の作成・確認
- 代行会社が、記事の骨子となる構成案(タイトル、見出し、各見出しで書く内容の要約など)を作成します。
- この段階で内容をしっかり確認し、認識のズレがあれば修正を依頼します。ここでのすり合わせが、記事の品質を大きく左右します。
執筆・校正・納品
- 構成案に沿ってライターが執筆し、編集者や校正者が品質チェックを行います。
- 完成した記事が納品されたら、内容を確認します。修正点があればフィードバックを行い、最終版を完成させます。
公開・効果測定
- 完成した記事を自社のWebサイトに公開します。
- 公開後は、PV数や検索順位などのデータを測定し、効果を検証します。月額プランなどでは、この効果測定と改善提案までをサポートしてくれる場合が多いです。[^5]
【実例】記事作成代行のよくある失敗事例3選とその対策
どんなに評判の良い会社に依頼しても、コミュニケーションや認識のズレから失敗は起こり得ます。
ここでは、よくある失敗事例とその対策を具体的に学び、同じ轍を踏まないようにしましょう。
失敗例1:「思っていた記事と違う…」品質・内容のミスマッチ
最も多い失敗が、納品された記事が期待していた内容や品質と異なっていたというケースです。
専門的な内容のはずが表面的な情報しか書かれていなかったり、ターゲット読者に響かないトーンになっていたりします。
- 原因
依頼内容の意図や目的が、代行会社やライターに正確に伝わっていない。 - 対策
- 目的・ターゲットの徹底共有: 「誰に、何を伝えて、どうなってほしいのか」を具体的に言語化して伝える。
- 構成案段階での入念な確認: 執筆に入る前の構成案の段階で、内容や方向性を徹底的にすり合わせる。
- 参考記事の提示: イメージに近い記事、逆にNGな記事の例を複数提示し、共通認識を作る。
失敗例2:「安かろう悪かろう…」低品質でブランドイメージが低下
コストを重視して格安のサービスに依頼した結果、誤字脱字だらけ、あるいは他サイトからのコピーコンテンツのような低品質な記事が納品されるケースです。
このような記事を公開すると、SEO評価が下がるだけでなく、企業の信頼性やブランドイメージを大きく損ないます。実際に、株式会社freeeは代行会社の選定を誤り、約120万円の潜在的な収益を失ったとされています。
- 原因
価格のみを基準に選び、代行会社の品質管理体制を確認しなかった。 - 対策
- 実績の確認: 制作実績を見て、品質レベルを確認する。
- トライアルの実施: 本契約前にサンプル記事の作成や少量発注で品質を確かめる。
- 品質管理体制のヒアリング: 編集・校正体制やコピペチェックの有無を必ず確認する。
失敗例3:「納期遅延で計画が台無しに…」マーケティング計画への支障
「月に10本記事を公開する」といったコンテンツマーケティング計画を立てていても、納期遅延が頻発しては計画倒れになってしまいます。
特に、新商品のリリースやキャンペーンに合わせて記事を公開したい場合、納期遅延は致命的です。
- 原因
代行会社の納期管理体制がずさん、あるいは無理なスケジュールで契約してしまった。 - 対策
- 納期管理体制の確認: 担当者やプロジェクトの管理方法について事前に確認する。
- 契約書での納期明記: 契約時に納期に関する条項を明確にし、遅延した場合の対応(違約金など)も取り決めておくと効果的です。
- 定期的な進捗確認: 丸投げにせず、定期的に進捗状況を確認し、遅延のリスクを早期に察知する。
記事作成代行の成功事例と今後の展望
失敗事例がある一方で、記事作成代行をうまく活用し、大きな成果を上げている企業も多数存在します。
- 株式会社CINC: SEO対策を施した記事作成により、アクセス数が90%増加。
- 株式会社PLAN-B: 記事経由での集客効果により、売上が35%増加。
- 株式会社グローバルリンクジャパン: 専門性の高い記事で、ブランド認知度が45%向上。
これらの成功事例に共通するのは、自社の目的を明確にし、それに合った信頼できるパートナーを選べている点です。
今後は、AI技術の進化により、記事作成のスピードはさらに向上し、コスト削減にも繋がっていくでしょう。
AIが作成した下書きを人間が編集・校正するという分業スタイルが主流になる可能性があります。
また、動画やインフォグラフィックなど、多様化するコンテンツへの対応力も代行会社に求められていきます。
企業はこれらのトレンドを捉え、最適なコンテンツ戦略を描いていくことが重要です。
まとめ:自社に最適な記事作成代行パートナーを見つけ、事業を加速させよう
記事作成代行サービスは、リソース不足に悩む企業にとって、コンテンツマーケティングを成功に導くための強力な武器です。
そのメリットは、時間と労力の削減、品質の向上、そして最終的な集客力や売上の向上に繋がります。
しかし、その効果を最大限に引き出すためには、自社の目的を明確にし、それに合った信頼できるパートナーを慎重に選ぶことが不可欠です。
今回ご紹介した選び方の8つのチェックリストを参考に、料金、実績、サポート体制などを総合的に比較検討してください。
- 目的とKPIを明確にする
- 実績と得意分野を確認する
- 料金体系と契約内容を隅々まで確認する
- SEO対策に関する知識と実績は十分か
- コミュニケーションとサポート体制は円滑か
- ライターや編集者の質と管理体制
- サンプル記事やトライアルで品質を確かめる
- 記事作成以外の対応領域もチェックする
もしあなたがBtoB企業のご担当者で、Webからのリード獲得や売上向上に本気で取り組みたいとお考えなら、ぜひ一度テクロ株式会社にご相談ください。
データに基づいた戦略と、クライアントに寄り添う伴走型支援で、あなたの会社の事業成長を加速させるお手伝いをします。
まずは無料相談や資料請求から、お気軽にお問い合わせください。
また、テクロが目指すのは、単発のコンテンツ制作ではありません。中長期的なマーケティング成果(リード獲得、商談化率アップ、ブランド形成)を見据え、戦略設計から伴走しながら、クライアントとともに成長するパートナーであり続けます。
導入事例から見るオウンドメディア運用代行サービス!
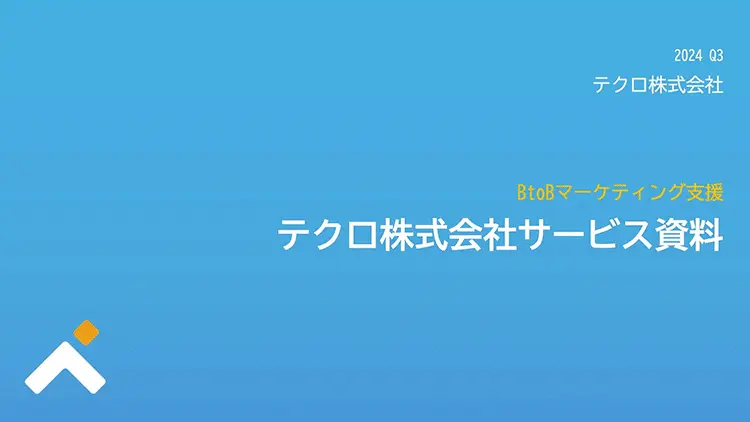
- 新たな集客手段を作りたい
- 問い合わせを増やしたい
- 運用を専門家に任せたい
オウンドメディアの立ち上げから実務まで代行した導入事例を紹介しています。「オウンドメディア支援サービス資料」をお気軽にダウンロードください。
記事作成代行サービスとは何ですか?
記事作成代行サービスは、企業や個人に代わって、専門のライターや編集者がWebサイトやブログに掲載する記事を作成するサービスです。